【介護サービスが必要になったら】介護の基礎知識(15)~介護休業給付金とは?概要や受給要件について~
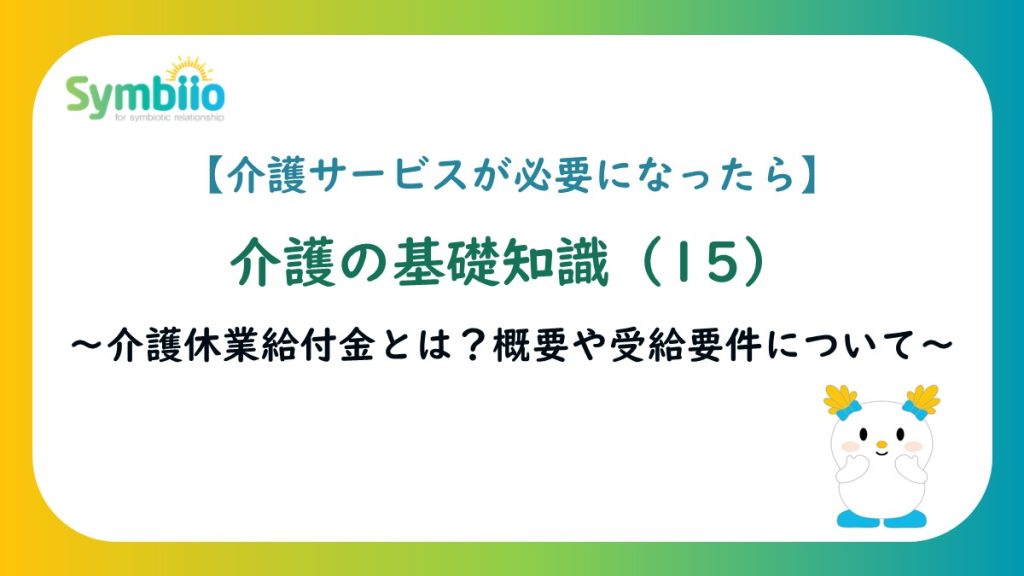
はじめに
家族に介護が必要になった場合、仕事と両立させることが大きな課題となってしまいます。
家族の介護のために仕事を休む、または辞めてしまうようなことになると収入が大きく減ってしまうため、経済的な不安を抱える方が多いのではないでしょうか。
そのような時に活用したいのが介護給付金制度です。
家族の介護のために仕事を続けることが難しい場合において、経済的な支援を受けられる制度となっています。
本記事では、介護休業給付金の概要や受給要件、受給の流れなどについて解説いたします。
介護休業給付金とは?
介護休業給付金制度は家族の介護のため、一時的に仕事を休む際に経済的な支援を受けられる制度です。
この給付金は雇用保険に加入している労働者が対象となり、休業中の収入減を補助するものです。
具体的には、休業開始時の賃金の67%が支給され、支給期間は最大93日間で、これを最大3回に分けて取得することができます。
この制度は介護と仕事の両立を支援し、労働者が職場復帰を前提に休業を取得することを目的としています。
介護休業給付金の受給要件
介護休業を取得する際には、介護休業給付金を受けるために特定の条件を満たす必要があります。
1.介護休業給付金の対象者
介護休業給付金の対象者は、雇用保険に加入していることが基本条件です。
具体的には、介護休業を始める前の2年間に通算で12カ月以上の雇用保険加入が必要で、介護休業中に雇用保険から脱退していないことです。
この12カ月については、以下のような規定もあります。
- ・月に11日以上の給与支払いがあれば、1カ月としてカウント可能。
- ・12カ月の雇用保険加入を満たしてなくても、1カ月に80時間以上の労働がある月は、
- 1カ月としてカウント可能。
給付金を受けるためには、介護休業開始前の6カ月間に介護対象者が要介護状態であることや、介護の必要性があるという医師の診断が必要です。
※証明書類については要介護状態にある事実を証明できるもので、労働者が提出できるものとなり、「医師の診断書」に限定されていません。
詳細な受給要件は厚生労働省の公式サイトで確認できます。
パート社員や派遣社員などの期間雇用者も対象ですが、介護休業を取得してから93日が経過し、
その後6カ月間は労働契約の満了が明らかになっていないことが条件となります。
2.介護休業給付金を受給できる条件
介護休業給付金を受け取るためには、いくつかの条件があります。
まず、介護休業を取得していることが必要です。
この給付金は事業主に介護休業を申請し、休業が終了した後に所定の手続きを経て支給されます。
介護休業の取得が必要かどうかの判断は事業主が行います。
また、介護の対象は親だけでなく、きょうだいや子ども、孫なども含まれます。
給付金をスムーズに受け取るためには、要介護度などの必要な情報を事前に調べておきましょう。
※介護休業の詳細は前章「介護の基礎知識(14)~介護休暇と介護休業の違いとは?取得条件や申請方法について~」をご参照ください
3.介護休業は職場復帰することが前提
介護休業は職場復帰を予定している方が対象です。
介護休業を取得する際、介護休業後に退職することが決まっている場合は取得できません。
また、介護休業を取得するためには、介護する家族が要介護状態である必要があります。
介護休業給付金が支払われないケースは?
1.産前・産後の休業中である場合
産前や産後の休業中は介護休業給付金の支給対象外です。
これは、産前産後休業には独自の支援制度があるからです。そのため、産前産後の休業中に家族の介護が必要になった場合でも、介護休業給付金を受け取ることはできません。
2.介護休業後に退職を予定している
介護休業終了後に職場復帰の意思があることも条件の一つとなっています。
もし介護休業の開始時点で退職が予定されている場合は給付の対象にはなりませんが、やむを得ず退職することもあるかもしれません。
その際は、転職して雇用保険を継続すれば給付金を受け取ることが可能ですが、雇用保険を継続しない場合は給付金を受け取れないため、注意が必要です。
3.介護休業期間中に一定条件下で就労した場合
介護休業中に就労することは可能ですが、いくつかの条件があります。
介護休業期間中に就労した場合、1支給単位期間において(1支給単位期間=介護休業開始日から1カ月のこと)、就労した日数が10日間を超えてしまうと、その支給単位期間は介護休業給付金が支給されません。
休業期間が1カ月未満の場合、給付金を受け取るためには就業日数が10日以下、かつ全日休業している日が1日以上必要で、さらに休業中の賃金が休業前の賃金と同じかそれ以上である場合は、給付金を受給することはできません。
具体的には、介護休業中の月々の賃金は、休業前の賃金の80%未満である必要があります。
まとめると休業期間中に11日以上の勤務があった場合は受給対象外となりますが、賞与については除外となります。
介護休業給付金の支給額はどのぐらい?
介護休業給付金=休業開始時賃金(日額)×支給日数×67%で計算します。
会社からの給与が13%未満の場合は67%分すべての給付が受け取れます。
しかし、会社からの給与が13%~80%の場合は80%までの差額、給与が80%を超える場合には支給額はゼロとなります。
具体例として休業開始時の賃金日額が10,000円(賃金月額300,000円)の場合の介護休業給付金を算出すると、以下のようになります。
①支給単位期間中に賃金が支払われていない場合
支給額=10,000円×30日×67%=201,000円
②支給単位期間に賃金が100,000円支給された場合
休業開始時賃金月額の80%=10,000円×30日×80%=240,000円
支給額=240,000円-100,000円(支払われた賃金)=140,000円
③支給単位期間に賃金が250,000円支払われた場合
→給付金は支給されません
支給される正確な金額は、ハローワークに提出した「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」をもとに算出されます。
給与の月額平均に応じた支給金の目安は次の通りです。ただし、給付金には支給限度額が設定されており、介護休業給付金の上限額は347,127円/月額になります。
月額平均
15万円の場合→支給額は約10万円
20万円の場合→支給額は約13万円
30万円の場合→支給額は約20万円
介護休業給付金の申請期間
介護休業は事業主に対して申請するため、通常は総務課や庶務課が窓口となります。
介護休業を取得するためには、開始予定日と終了予定日を決め、開始日の2週間前までに必要な書類を会社に提出します。
会社の就業規則に従って手続きが行われるため、事前に就業規則を確認し、担当者に相談しましょう。
1.給付金の申請先と申請期間
給付金申請書は在職中の事業所の所在地を管轄するハローワークに申請し、申請手続きは基本的に事業主を通じて行われます。
2.給付金申請に必要な書類
介護休業給付金の支給を受けるためには「介護休業給付金支給申請書 」と「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」をハローワークに提出します。
さらに以下のような書類の内容を証明する添付書類も必要です。
【受給資格確認に必要な書類】
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」(賃金台帳や出勤簿またはタイムカード等)
【支給申請に必要な書類】
①「介護休業給付金支給申請書」
(マイナンバーを記載)
②被保険者が事業主に提出した介護休業申出書
③介護対象者と申請者の続柄などが確認できる書類(住民票記載事項証明書など)
④休業日数の確認ができる書類
(出勤簿、タイムカードなど)
⑤休業中の賃金支払い状況が確認できる書類(賃金台帳など)
介護休業給付金支給申請書などの必要書類は、通常は事業主がハローワークに提出しますが、休業する本人が直接提出することもできます。
3.支給決定通知と支給される時期
支給申請の結果は「支給決定通知書」または「不支給決定通知書」で通知されます。
介護休業給付金支給申請書には希望する金融機関を記入する欄があります。
申請期間は介護休業終了日の翌日から2カ月以内で、支給決定後は指定した金融機関の口座に約1週間後に振り込まれます。振り込みに関する問い合わせは厚生労働省ではなく、ハローワークで行います。
4.給付金支給の流れ
①介護休業開始日の2週間前までに事業主に介護休業を申請する
※会社によって詳細が異なる場合があるため、事業主に確認してください
②介護休業開始
③対象家族につき1回の介護休業終了
④受給資格確認と給付金支給申請を同時に行う
⑤支給(不支給)決定を受け、支給決定通知書が交付される
⑥支給決定日からおおむね1週間程度で指定口座に給付金が振り込まれる
介護休業利用時の注意点とポイント
1.介護休業中は給付金がもらえない
この給付金は休業が終了した後に申請するため、介護休業中に受給することはできません。
休業が終わった後に手続きを行うことを忘れないようにしましょう。
2.介護休業給付金制度の利用は原則一度まで
介護休業給付金は同じ被介護者に対して一度だけ受け取ることが原則です。
しかし、93日分の介護休業を最大3回に分けて取得することができ、被介護者の状況に応じて休業期間を調整することが可能です。
また、同じ家族が介護を行う場合でも、被介護者が異なれば再度介護休業を取得することができます。
例えば、Aさんが母親の介護のために93日の介護休業を取得した後、父親の介護に対しても再び93日の介護休業を利用することができます。
3.要介護度が変わっても制度利用は原則1回
具体例として、要介護4の母の介護のため70日分連続で介護給付金を受け取っていた場合、要介護度が5に変わったとしても、介護休業給付を受けられるのは、残り23日分(全93日)までとなります。
4.複数人が介護する場合も給付金を受けることができる
介護休業は同じ被介護者に対して複数人が時期をずらして取得したり、同じ被介護者に対して複数人が同時期に取得することができます。
例えば、祖父の介護をするために、夫、妻、孫がそれぞれ93日間の介護休業を取得することが可能です。また、複数の介護者が同時に介護休業を取得することも認められています。
給付金の支給要件を満たすことで、各介護者は介護休業給付金を受け取ることができるため、家族間で休業のタイミングを調整し、より良い介護環境を整えましょう。
5.介護休業期間が2週間未満でも給付金は受給できる
厚生労働省によると、介護休業給付金を満たす条件の一つに「負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障がいにより、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族を介護するための休業であること」というものがあります。
例えば、休業に入ったものの、早めに介護施設へ入居できたため、実際の介護休業日数は10日で済んだという場合、10日分の介護休業給付を受けることができます。
おわりに
介護休業給付金制度は働きながら家族を介護する方を経済的に支援するための制度であり、この給付金は介護のために仕事を休む必要がある場合に、特定の条件を満たすことで受給することができます。
介護が必要な状況になった際、仕事と両立させながら慣れない介護をしていると、非常にハードな場面や状況に出くわすことも出てきてしまいます。そういったことが続くと介護者の負担は増大し、心身に大きく影響してしまいます。
そのような時は一人で抱え込むことなく、介護休業や給付金制度、そして様々なサービスを上手に活用して、仕事と介護を両立させられる環境を整えていきましょう。
トピックス【介護サービスが必要になったら】記事のご案内
過去の記事をまとめてございます。よろしければご参照ください。
参考リンク
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158665.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001280390.pdf
みんなの介護