【介護サービスが必要になったら】介護の基礎知識(13)~訪問介護と居宅介護の違いとは?~
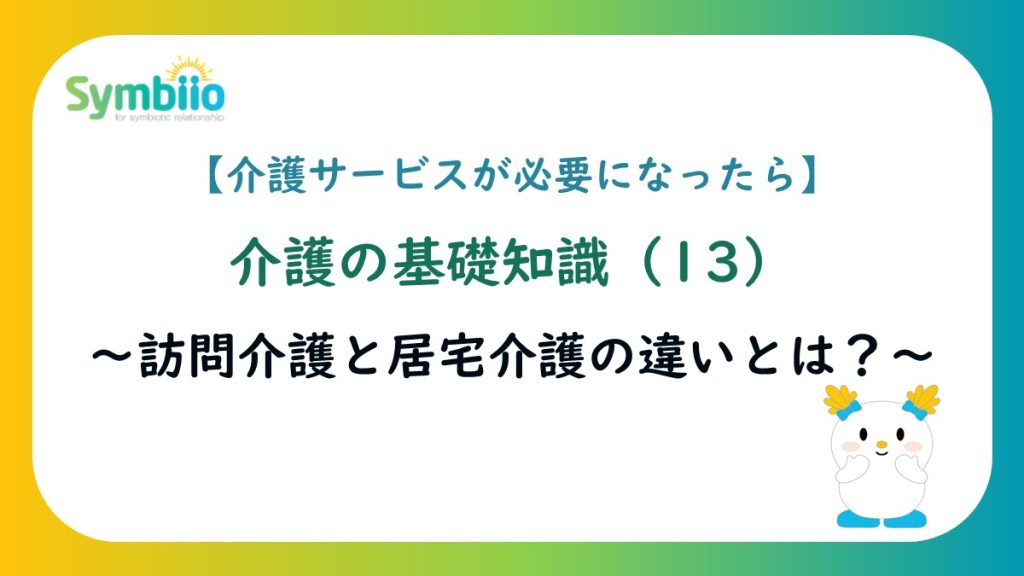
はじめに
自宅で利用できる介護サービスの中で「居宅介護」と「訪問介護」というものがあります。
このサービスは名称が似ているため、両者の違いが分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では居宅介護と訪問介護のサービスの違いや対象となる方、利用料金などについて解説いたします。
訪問介護と居宅介護の違いとは?
訪問介護と居宅介護は、いずれも在宅サービスに分類されますが、法的な枠組みと目的において大きな違いがあります。
訪問介護は介護保険法に基づき、高齢者が身体機能の低下に伴い利用できるサービスです。
これに対して、居宅介護は障がい者総合支援法に基づき、障がいを持つ方々が自立した生活を送るための支援を目的としています。
また、居宅介護と居宅介護支援も異なるサービスです。
居宅介護は障がい者が自宅での生活を充実させるための介護サービスで、日常生活の支援や身体介護が含まれます。
一方、居宅介護支援は介護が必要な人が最適な支援を受けるための手続きを代行するサービスで、介護保険法に基づく保険給付対象となります。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
訪問介護とは?
自宅で生活する高齢者に対して、介護福祉士やホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助を行います。
訪問介護は要介護1~5の認定を受けた方を対象としています。
要支援1・2の方は「介護予防訪問介護」を利用することができ、こちらは介護予防を目的としたサービスで、主に生活援助が中心となります。
居宅介護とは?
居宅介護は障がい者総合支援法に基づく障がい福祉サービスの一つで、利用者は身体介護や家事援助、その他の生活全般にわたる支援を受けることができます。
18歳以上64歳未満の身体障がい、精神障がい、知的障がいを持つ方が対象で、障がい支援区分1以上と認定された方や、18歳未満の障がい児も含まれます。障がい支援区分が2以上の方でも、一定の条件を満たす場合には居宅介護の対象となることがあります。
詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください。→こちらからどうぞ
居宅介護支援とは?
居宅介護支援とは介護保険法に基づくサービスの一つで、介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、心身の状況や環境に応じたケアプランを作成するとともに利用者と事業者との橋渡し役も果たします。
このサービスは自宅で生活する高齢者や要介護1〜5の認定を受けた方を対象としています。
要支援1・2の方については、地域包括支援センターの介護支援専門員がケアプランの作成を担当します。
※2024年4月からこれまで地域包括支援センターから委託を受けて行っていた(要支援の)介護予防支援が、居宅介護支援事業者でも実施できるようになりました
サービス対象者の違い
訪問介護の場合
訪問介護は主に65歳以上の高齢者を対象としていますが、特定疾病を持つ40歳から64歳の方も利用可能です。
訪問介護を受けるには、まずケアマネジャーにケアプランを作成してもらいます。その後、サービス事業者との調整を行い、契約を結んだ事業所から訪問介護員が派遣されます。
ケアプランは自分で作成することもできますが、時間や手間を考慮すると、ケアマネジャーに依頼するケースが一般的です。
居宅介護の場合
居宅介護サービスの利用については障がい者自立支援法による条件が定められています。
居宅介護の利用対象者は、障がいの種類や年齢によって異なります。
具体的には、18歳以上の身体障がい、精神障がい、知的障がいを持ち、障がい支援区分1以上に認定された方や、18歳未満で同等の障がいを持つ児童が対象です。
また、指定難病や特殊な疾病、事故やケガによる肢体障がいや視覚障がいを持つ方も、障がい支援区分に認定されていればサービスを受けることができます。
居宅介護サービスを利用する際は、まず基幹相談支援センターに相談し、計画作成相談を行います。その後、指定特定相談支援事業者がサービス事業者と調整し、訪問介護員が派遣される流れになります。
共生型サービスとは?
障がい福祉サービスを利用していても、介護保険が優先されるため65歳になると介護保険サービスに切り替わります。
これまでは利用者が65歳になると居宅介護を行っている事業者から、訪問介護の指定を受ける事業所に変更する必要があり、計画作成者も相談員からケアマネジャーに変わるため、サービスの継続が難しい状況でした。
しかし平成30年から共生型サービスが導入され、障がい者自立支援法と介護保険法の両方の指定を受けている事業者が増え、利用者は制度が変わっても同じ事業者からサービスを受け続けることができるようになりました。
サービス内容の違い
居宅介護と訪問介護は、提供されるサービスにほとんど違いがありません。
主なサービス内容は、身体介護と生活援助に分かれます。
身体介護には排泄や入浴、更衣、服薬の介助が含まれ、生活援助では調理、掃除、買い物などが行われます。
居宅介護や訪問介護を利用するための条件を満たすと、他にも多様なサービスを利用することが可能です。具体的には、障がい者自立支援法に基づく重度訪問介護や同行援護、介護保険に基づく通院等乗降介助などがあります。
利用料金の違い
・訪問介護
訪問介護の料金は介護保険に基づいて決まっており、自己負担額は所得により1割~3割負担です。
基本的には1割負担のため、30分未満の場合の目安として、身体介護の場合は166円~577円、
生活援助の場合は182円~224円となります。
例えば、週2回の訪問の場合、月の自己負担額は通常5,000円~1万円程度です。
初回加算や早朝・深夜の加算があると料金が増加することがあります。
・居宅介護
居宅介護は障がい者自立支援法に基づき、厚生労働省が定めた障がい福祉サービス費が適用されます。
居宅介護も訪問介護と同じようにサービスの内容や時間によって料金が異なり、利用者は基本的に1割負担で、目安として30分未満のサービスの場合、身体介護は255円、家事援助は105円から利用可能です。
おわりに
「居宅介護」と「訪問介護」の大きな違いとして、対象になる方の違いが挙げられますが、どちらも介護が必要な高齢者や障がい者が自宅で自分らしい生活を続けられるよう支援する公的なサービスであるということが分かりました。
障がいをお持ちの方は65歳になったら介護保険への切り替えが可能となり、ここからは訪問介護のサービスを利用することができます。このサービスを利用すれば必要な支援を受けながら自宅での生活を維持することができますので、上手に活用して暮らしやすい環境づくりを目指していきましょう。
トピックス【介護サービスが必要になったら】記事のご案内
過去の記事をまとめております。よろしければご参照ください。
参考リンク
厚生労働省
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group2.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html