【介護サービスが必要になったら】介護の基礎知識(12)~グループホームとは?②サービス内容について~
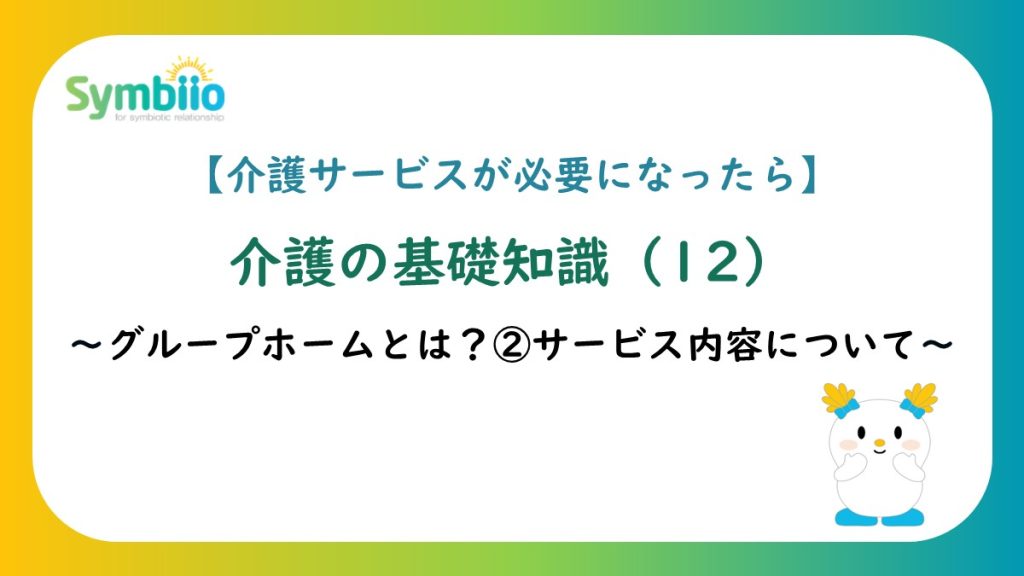
はじめに
前回はグループホームの概要や入居条件、必要とされる費用などについて解説させていただきました。
今回の記事ではグループホームで受けられる具体的なサービス内容や、入居した際のメリット・デメリット、さらに入所までの流れなどについて解説いたします。
グループホームの主なサービス
グループホームでは、認知症に特化した専門知識を持つ介護スタッフが利用者に対して多様なサービスを提供しています。
認知症になると自立した生活が難しいと考えられがちですが、実際には家事や身の回りの事が全くできなくなるわけではありません。
グループホームでは利用者がスタッフのサポートを受けながら料理や洗濯などの家事を行っており、
利用者同士で役割分担をしながら、できることとできないことを考慮したケア体制が整っています。
・介護サービス
多くの施設で食事の提供や掃除、洗濯といった基本的なサービスが行われています。
また、見守りや生活相談、食事や入浴、排泄の介助、着替え介助といった支援も充実しています。
・認知症ケア
認知症介護において、専門スタッフが日常生活のサポートやメンタルケアも行っています。
具体的には、思い出の写真を飾ったり、愛着のある物を身近に置いたりすることで、心のケアに対する工夫が行われています。また、施設内のレクリエーションやリハビリにとどまらず、地域との交流も図っており、最近では地域の祭りに参加したり、公園の清掃活動に協力するなど、地域とのつながりを強化する取り組みが増えているそうです。
・食事
入居者が献立決めに関わるホームもあり、料理が苦手な方でも安心して参加できるように工夫がされています。基本的に1日3食提供されており、おやつが出るホームもあります。
・レクリエーション
レクリエーションに関しては有料老人ホームと同様の活動が多く、特に認知症に効果的な手先を使った作業や音楽療法、回想療法、アニマルセラピーが中心となっています。
施設内では、スタッフと共に買い物や食事の準備、清掃などの家事を行うことで、日常生活がリハビリの一環となり、認知症の進行を緩和することを目的としています。
・医療
グループホームは有料老人ホームとは異なって、看護師の配置義務がありません。
そのため、看護師不在の施設が多いことが実状です。
日常的な健康管理は施設の介護スタッフが行うことが一般的ですが、最近では看護師を配置したり、
訪問看護ステーションと連携を強化する施設も増えてきています。
・看取り
グループホームは身体症状が安定している方の生活の場であるため、医療体制が不十分な施設が多いという現状があります。
高齢化が進む中でグループホームの入居者も高齢化し、近年では看取りに対する関心が高まっていますが、看取りに対応している施設はまだ少なく、病院や介護施設への転居が必要になることもあります。
入居者が慣れ親しんだ場所で穏やかに最期を迎えたいと考える場合は、事前に施設に確認することをお勧めします。
グループホームのメリット・デメリットについて
グループホームは共同生活ができる程度の自立を求める施設です。
入居者が寝たきりになったり、治療が必要な状態になった場合は、医療行為が可能な他の施設への転居が必要になるケースもあります。
グループホームのメリット
認知症ケアに特化していること
グループホームに常駐する職員は、認知症ケアに関する豊富な知識と経験を持っています。
認知症ケア専門のスタッフの支援を受けながら、入居者は料理や洗濯などの家事を自分で行うことが基本となっており、このような自立した生活は認知症の進行を遅らせたり、症状を和らげる可能性があるとされています。
重要なのは、認知症の高齢者に対して「何もできない」と決めつけるのではなく、入居者が持つ残存能力を活かすことです。
少人数でアットホームな雰囲気
グループホームの特徴として、少人数でアットホームな雰囲気であることが挙げられます。
通常、5人から9人で構成されるユニットごとに共同生活をするため、入居者はより親密な関係を築くことができます。
認知症を抱える高齢者にとって、大人数の施設はストレスの原因となることが多く、認知症の症状によって顔や名前を覚えることが難しくなるため、他者との関わりが億劫になることもあります。
そのため少人数の環境であれば、他の入居者や職員と顔なじみになることができ、安心感を得ることができます。
長年住んだ地域から離れずに済むこと
グループホームは高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるように設計された地域密着型のサービスです。
入居者が慣れ親しんだ環境を維持できるため、環境の変化によるストレスを軽減できます。
また、同じ地域に住んでいる人々が共同生活を送ることで、入居者同士のコミュニケーションが促進されるというメリットもあります。
有料老人ホームに比べて低価格
グループホームの初期費用は数万円から数十万円程度で、有料老人ホームに比べて低いことが特徴です。
有料老人ホームの初期費用は施設やサービス内容によって異なり、数百万円から数千万円にのぼることもあります。月額費用については、グループホームが一般的に10万円から20万円程度であるのに対し、有料老人ホームは10万円から30万円と幅があります。
グループホームのデメリット
住民票が入居希望施設の市区町村にあることが条件
住民票のある市区町村の施設に入居することがグループホーム利用の条件であるため、希望するグループホームが住民票のある地域にない場合、他の地域の施設には入居できません。
住み慣れた地域での生活を維持することはできますが、選択肢が制限されることになります。
医療ケアが充実していないこと
グループホームの多くは医療スタッフ・看護スタッフが常駐していないため、医療面でのケアが十分ではありません。
専門的な診療や治療が必要な場合、利用者は医療機関に出向く必要があることが多いです。
充実した医療ケアを希望する場合は、医療・看護スタッフが常駐している施設を選びましょう。
施設の空きが少ないこと
グループホームは原則として最大18人までしか入居できません。
高齢化に伴い認知症を患う方が増えるにつれ、認知症の方の全体数も増え続けています。そのため、グループホームへの需要が高まっていますが、施設の定員数が決まっているために、すぐに入居できないことがデメリット要因の一つです。
グループホームへの入居を検討している場合は、早めに複数の施設を選び、仮申し込みを行うことをおすすめします。
要介護度が上がると退去が必要な場合がある
グループホームの入居条件は要支援2または要介護1以上の認知症患者に限定されています。
自立した生活を前提としているため、入居者の要介護度が上がって自立した生活が困難になると、退去を求められることがあります。
認知症ケアのサービスは認知症の進行を遅らせることを目的としていますが、症状を改善させるという点においては、あまり期待ができません。そのため、認知症が進行して要介護度が上がると、転居が必要になる可能性があることを念頭に置いておかなければいけません。
グループホームで使える減額制度
・高額介護サービス費制度
高額介護サービス費とは、介護保険の1カ月の自己負担額の合計が上限を超えた場合に、その超過分が払い戻される制度です。
上限額は所得に基づいて設定されており、この制度は公的介護保険の自己負担部分に適用され、理美容代や居住費などの雑費には利用できません。
一度申請を行うと、以降は該当する度に支給されますが、支給申請には2年の時効があるため、更新を忘れないようにしましょう。
・家賃の助成制度
家賃の助成制度は、月額1万円を上限として家賃補助を提供する制度で、低所得世帯や生活保護受給者を対象としています。申請が承認されると、助成金は施設側が受け取り、家賃からその金額が差し引かれる仕組みになっています。
・市区町村の助成金
自治体によってはグループホーム入居者に対して独自の助成金を支給している場合があります。
助成金の利用要件は自治体ごとに異なり、住民税非課税世帯や収入、資産に関する条件が設けられていることが多いです。市区町村の福祉健康窓口や介護保険窓口に問い合わせて、助成金の有無や具体的な内容を確認することをおすすめします。
・社会福祉法人による軽減制度
社会福祉法人が運営するグループホームでは、低所得者向けに利用者負担軽減制度を実施している場合があります。
施設の種類や利用者の収入によっては、介護保険サービス費の自己負担分や食費・居住費が軽減されることもあり、これらの軽減措置は施設の種類や利用者の収入によって異なるため、具体的な内容や利用条件については、各施設に直接お問い合わせください。
グループホームを選ぶときの注意点
グループホーム選びで失敗しないためには、候補を絞る際に費用、介護体制、医療体制などの基本条件をしっかり確認することが大切です。
見学時には、ホーム内の雰囲気やスタッフの表情にも注目しましょう。
希望エリアに複数のグループホームがある場合は、運営推進会議に参加することもおすすめです。
この会議には自治体の職員や担当の地域包括支援センター職員、関わりのある地域住民も参加していることが多いため、入居者の生活状況を聞くことができ、管理者やスタッフがどのような運営方針を持っているかを知る良い機会です。
運営推進会議は誰でも参加でき、地域の職員や住民も多く参加しているため、情報交換の場としても有効です。また、家族会が同日に行われることも多く、入居者自身が参加することもあります。会議の雰囲気からそのグループホームがどのような所かを把握することもできます。
グループホーム見学時に見るべきポイント
・入居費用
無理のない資金計画を立てることが重要になりますので、長期的に入居できる施設を選ぶ際には、経済的な負担を考慮する必要があります。
・医療体制
持病がある方や、今後医療行為が必要になる可能性が高い方は、医療行為に対する対応が可能かどうかをしっかりと確認することが重要です。
・介護体制
スタッフの数や定着率を確認しておくことも大切で、特に認知症が進行すると徘徊などの特有の症状が現れるため、スタッフの介護体制が整っているか確認することが重要です。認知症でうまくコミュニケーションが取れない方などに、どのように対応しているか確認しましょう。
・入居者の状況
入居者の表情が穏やかであれば、認知症の状態が安定していることを示していることが分かります。
一人ぼっちになっている人がいないかどうかも重要な見学ポイントです。
見学時には、入居者がスタッフと一緒にどのような活動を行っているかを確認することが大切です。
料理や洗濯物を畳むこと、レクリエーションなど、共同作業が多いほど望ましいとされています。
グループホームでは日常生活の動作が機能訓練の役割を果たすため、入居者同士やスタッフとの交流が重要となってきます。
ショートステイや体験入居をする
グループホームではショートステイ(短期入居)や体験入居が可能です。
短期入居は介護サービスの一環として利用されるため、自宅でのケアを担当しているケアマネジャーと相談し、ケアプランの作成が必要になります。
一方、体験入居は保険適用外ですが、グループホームの利用を通じて得られる情報が多く、入居先を探している方にはおすすめです。
入居の手続きと流れ
グループホームへの入居手続きは、各施設で直接行うことが原則です。
入居までの一般的な流れは以下の通りです。
①見学や面談
↓
②入居申し込みと必要書類の提出
↓
③本人面談
↓
④入居可否の決定
↓
⑤入居契約
一般的に、グループホームへの入居には約2~3カ月の時間が必要です。
しかし、現在の状況では入居の難易度が高く、施設によっては数カ月から数年の待機時間が発生することがあります。グループホームは地域密着型サービスであるため、入居できるのはその地域に住んでいる方のみで、各施設の定員は原則18人(1ユニット9人、最大2ユニット)と小規模です。
このような制約が入居を難しくさせる要因の一つとなっています。
おわりに
グループホームは認知症の高齢者に特化した介護サービスを提供する施設であり、特徴であるアットホームな環境と住み慣れた地域で生活できるため、入居者にとっては安心感があります。
日本の高齢化が進む中で、グループホームの需要は年々増加しています。
施設選びの際には、費用の相場や提供されるサービスの詳細を確認することが大変重要なポイントとなっておりますので、先々の事を見据えながら、穏やかに過ごせる環境を選びましょう。
トピックス【介護サービスが必要になったら】記事のご案内
過去の記事をまとめております。よろしければご参照ください。
参考リンク
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000647295.pdf
公益財団法人 長寿科学振興財団 健康長寿ネット
https://www.tyojyu.or.jp/net/kaigo-seido/chiiki-service/group.html