【介護サービスが必要になったら】介護の基礎知識(6)~有料老人ホームとは?②入居までの流れについて~
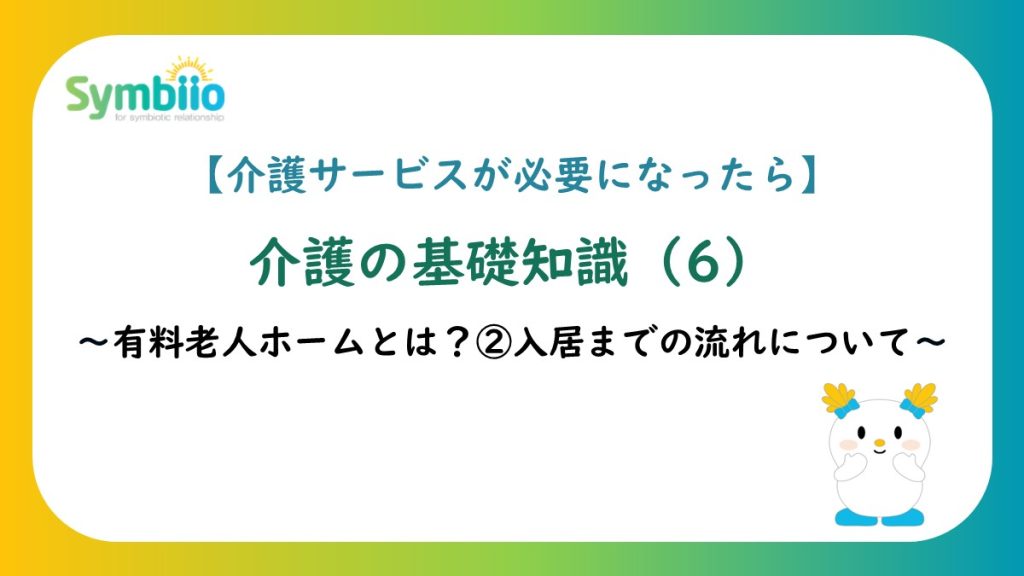
はじめに
前回の記事では有料老人ホームの概要や他の介護施設との違い、選び方などについてお話させていただきました。
今回は有料老人ホームへの入居をお考えの方に向けて、入居するまでの流れや施設選びのポイントなどについて解説いたします。
有料老人ホームの入居条件
1.介護付き有料老人ホームの入居条件
介護付き有料老人ホームでは軽度の認知症の方の受け入れも可能です(施設によっては重度の認知症の受け入れも可能)。
「介護専用型」は要介護1~要介護5の方で、「混合型」は自立~要介護5の方が入居できます。
介護付きで利用できる「特定施設入居者生活介護」は、要介護1以上の認定を受けた方が対象です。
そのため「介護専用型」の施設では、原則として65歳以上で要介護1以上の認定を受けている方が入居条件となります。
2.住宅型有料老人ホームの入居条件
「住宅型」の施設では、認知症でも軽度であれば入居できる施設があったり、各施設ごとに具体的な入居条件が異なるため、事前に確認することが重要です。
「住宅型」の施設では介護や看護の体制が十分でない場合があり、そのため介護度が高い方や重度の認知症の方、持病を持つ方の入居が難しいことがあります。
3.健康型有料老人ホームの入居条件
健康型有料老人ホームはアクティブシニアを入居者として想定しているため、基本的に要介護認定を受けている方や、日常的に医療的処置を必要とする方は入居の条件に当てはまりません。対象の入居時年齢は60歳または65歳以上に設定されています。
入居のタイミング
有料老人ホームへの入居を考える際、「どのタイミングで入居すれば良いのか」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
入居のタイミングには家庭環境や生活状況によって異なりますが、一般的には3つのパターンがあるとされています。
①元気なうちに
自立して生活している方々の中には、将来に備えて元気なうちに有料老人ホームに入ることを選ぶ方もおり、早めに施設を探すことで、自分の好みやライフスタイルに合った施設を見つけやすくなるというメリットがあります。
②病院から退院時に
高齢になって病気や怪我で入院した後、退院時に要介護状態になることがあります。
退院後に自宅での在宅介護が難しい場合、有料老人ホームへの入居が選択肢となったり、また、リハビリを目的として介護老人保健施設(老健)に入居することもあります。
老健は入居期間が限られているため、退院後に老健に入居し、その後有料老人ホームに移るケースも多く見られます。
③在宅介護に限界を感じた場合に
仕事と介護を両立させている介護者は、要介護者の状態が悪化するにつれて、身体的な負担や精神的なストレスが増加し、限界に達する可能性があります。このような場合には、有料老人ホームへの入居を考えてみましょう。
限界を感じてから施設を探し始めても、本人に合った施設をすぐに見つけられるとは限りません。
そのため、介護者が限界を感じる前に、あらかじめ施設入居の準備を進めることをお勧めします。
将来に不安を感じた際には、早めに行動を起こすことが大切です。在宅介護は無理をせず、施設入居を検討してみてください。
入居するまでの流れ
1.希望条件を決める
まず希望する地域を決めましょう。
自宅からの距離を重視するのか、場所にこだわらないのかを考えましょう。
次に、入居者本人に必要な医療や介護サービスの程度を把握することが重要です。
特に認知症や特別な医療処置(胃ろうやストーマ、喀痰吸引、透析など)が必要な方の場合、
施設がその受け入れ体制を整えているかどうかを確認することも必要です。
希望する条件が整理できたら、次は施設の種類を検討します。
有料老人ホームの場合、要介護状態なら「介護付き」、自立した生活ができるなら「住宅型」というのが基本的な選択肢です。
立地や身体の状態・介護度に適した施設を絞り込めたら、さらに細かく条件の絞り込みを行います。
予算やサービス内容、施設内のアクティビティやイベントなど、さらに具体的な条件を考慮して選択を進めます。
2.情報収集をする
有料老人ホームの情報収集にはインターネットの検索サイトを利用するのが最も効率的です。
希望条件を設定して検索することで、より自分のニーズに合った施設を見つけることができます。
老人ホームの情報を集めたら、その中で特に気になる施設をピックアップし、パンフレットを取り寄せます。
要介護認定を受けている場合は、担当のケアマネジャーに相談するのがよいでしょう。
また、入院中であれば病院のソーシャルワーカーに尋ねることで、地域の施設情報を得ることができます。
さらに、役所の高齢者福祉相談窓口や地域福祉協議会、地域包括支援センターでも、地域内にある有料老人ホームの一覧表を配布していたり、無料の紹介センターを案内してくれる場合があります。
3.見学や体験入居をしてみる
候補を数件まで絞り込めたら、現地に行って見学をします。
入居者本人が見学するのが望ましいですが、健康上の理由で難しい場合は家族が代わりに見学しましょう。見学前に確認すべきポイントをメモしておくと、見学時にスムーズに確認できます。見学時のチェックポイントは、大きく分けて「建物や設備」「職員」「サービス内容」「契約内容」の4つがあります。
見学を行った後、体験入居を一度しておくことをお勧めします。
体験入居を通じて、入居者から施設に関するリアルな情報を得ることができ、施設の設備や館内の環境、スタッフのサービス内容を実際に確認することができます。入居後のトラブルを避けるために具体的な情報を集めておきましょう。
4.仮申し込み・面談
見学を通じて気に入った場合は、可能であれば仮申し込みをしましょう。
仮申し込みはキャンセルしてもペナルティがないため、少しでも興味があれば積極的に行動することが大切です。
入居に際しては、健康診断書や診療情報提供書などの書類を提出する必要があるため時間がかかることがあり、入居予定者が入院中の場合だと書類は1週間ほどで作成されることが多いですが、入院していない場合は主治医に依頼する必要があるため、およそ2~3週間かかることもあります。
そして書類提出後には、施設スタッフと入居検討者との面談が行われます。
多くの施設ではスタッフが訪問しますが、場合によっては入居検討者が施設に足を運ぶ必要があることもあります。この面談は、施設での受け入れが可能かどうかを判断するための重要なステップです。
5.入居契約をする
入居を希望する施設を選んだ後は、施設側と入居契約を結ぶことになります。
この際、特に重要なのが「重要事項説明書」の内容です。
この書類は運営会社の情報や入居費用、施設の建物・設備の概要、職員の配置体制、サービスの内容などがすべて記載されており、契約に関する重要な情報を施設側が入居者に説明するためのものです。
契約前に施設の職員が説明を行うため、内容をしっかり確認することが重要です。
もし説明された内容が事前に理解していたものと異なる場合は、必ず質問して確認しましょう。
契約は急ぐ必要はなく、重要事項説明書をじっくり読み、疑問点を解消してから契約を進めることが大切です。疑問を残したまま契約を結ぶと、後々トラブルに発展する可能性があります。
有料老人ホームを決めるポイントや注意点
有料老人ホームに入居する際は、事前の準備と情報収集が非常に重要です。
入居後に「合わなかった」「住み替えが必要」といった状況になると、退去手続きや新しい施設探し、さらに引越し作業が必要になり、体力的にも金銭的にも非常に大きな負担がかかります。
失敗を避けるためには、慎重に施設の選択を行うことが重要です。
1.入居条件に適しているか
入居条件については入居時だけでなく、将来的に介護度や医療的なケアの必要性が高まったり、長期入院が必要になった場合でも引き続き居住できるかを確認しましょう。
元気なうちだけの居住先を探している場合は、あまり気にする必要はありません。
しかし、入居先の施設の長期利用をお考えの場合は、将来の状況変化を見据えて、入居条件を事前に確認しておくことが重要です。
2.施設の雰囲気や住環境について
有料老人ホームを選ぶ際には長期的な利用を考慮し、良質な環境を求めることが重要です。
施設の外観だけでなく、施設内の雰囲気の良さや居室の設備も確認する必要があります。事前の見学は必須で、疑問点はしっかりと質問して解消しましょう。
また、スタッフの対応にも注目し、笑顔や適切な言葉遣い、質問への回答の質を確認することが大切です。スタッフが丁寧に対応し、利用者と積極的にコミュニケーションを取っているかもチェックポイントです。
3.希望する介護サービスが提供されているか
有料老人ホームを選ぶ際には、希望する介護サービスが提供されているかどうかが重要なポイントです。
施設ごとの理念やサービスの提供方針はさまざまです。外出やレクリエーションを重視する施設もあれば、日常生活の自立支援に力を入れている施設もあります。外出やレクリエーションを楽しみたい場合は、過去のイベントや今後の予定を確認することが有効です。
具体的な介護サービスや食事内容については、希望に合った施設かどうかの判断がしやすくなるため、体験入居を利用して実際に確認することをお勧めします。体験入居が難しい場合は、食事の時間帯に合わせて見学することで、実際の生活の雰囲気を感じることができます。
4.家族が会いに行きやすい場所にあるか
ご本人が住み慣れた地域の施設を選ぶことが一般的には多いですが、家族がアクセスしやすいかどうかも重要なポイントになりますので、車や公共交通機関でのアクセスを事前に確認しておくことをお勧めします。
また、施設によっては家族参加型のイベントや面会用の宿泊室やリビング・ダイニングが設けられている場合があります。家族が頻繁に訪れることを想定し、実際に施設を見学して確認することが望ましいです。
さらに「家族会」などの交流の場があるかどうかも確認しておくと良いでしょう。パンフレットに情報がない場合は、見学時に質問して確かめましょう。
5.医療機関との連携体制が整っているかどうか
医療や介護のケア体制を確認することも重要ですが、医療機関との連携体制について、どの医療機関と連携し、対応範囲がどこまでかを把握しておくことも必要となります。
また、緊急時の対応方法を事前に確認しておくことで、万が一の際にも安心して任せることができるでしょう。
有料老人ホームで介護保険適用となるサービス
介護付き有料老人ホーム・住宅型有料老人ホーム・健康型有料老人ホームの3種類のうち、介護付き有料老人ホームは名前の通り介護保険が適用されたサービスを受けることができますが、それに対して住宅型・健康型は施設の利用に対して介護保険が適用されません。
住宅型・健康型の有料老人ホームでは、施設の利用条件や受け入れ可能な利用者の介護度が異なり、自立した高齢者も対象となるためです。ただし、住宅型有料老人ホームでは、外部の介護サービス事業者と契約することで介護保険適用のサービスを受けることが可能です。
①介護付き有料老人ホーム
介護付き有料老人ホームでは、具体的には食事の提供、入浴の介助、排泄のサポート、着替えの手伝い、移動時の介助などが介護保険の適用を受けることができます。
②住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームでは、在宅での介護保険適用サービスと同様に訪問介護やデイサービスを利用することができます。
特に「住宅型」の特徴として、自宅で受けていたサービスを入居後も継続して利用できる点が挙げられます。この点は「介護付き」施設にはないメリットです。
介護保険の住所地特例とは?
介護保険では原則として居住している市町村の被保険者となりますが、施設に入所された方を一律に施設所在地の市町村の被保険者とすると、介護保険施設等が集中して建設されている市町村の介護保険給付費が増加し、市町村間に財政的な不均衡が生じます。
そこで市町村間の保険料負担を均等にするために設けられたのが、「住所地特例」という制度です。
介護保険の被保険者の方が、お住まいの市町村から他の市町村の介護保険施設や有料老人ホーム等に入所して施設所在地に住民票を移された場合に、引き続き元の市町村の被保険者となる制度です。
住所地特例は、それまで住んでいた市町村以外の場所にある高齢者施設や有料老人ホームに入居した場合に適用されます。
自宅と同じ市町村にある施設に入った場合は、この特例の対象外となります。
介護サービス費用を軽減するための制度
高額介護サービス費制度
高額介護サービス費は、介護サービスの月額費用が一定額を超えた場合に介護保険から支給を受けられる制度で、この「一定額」は世帯の所得区分によって異なります。
重要なのは、支給対象となるのは介護サービスの自己負担額のみであり、賃料や食費、管理費などは対象外となる点です。
制度を利用するためには市区町村への申請が必要です。
高額介護合算療養費制度
高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険における1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の
自己負担額が負担上限額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。
負担上限額は各所得の区分によって異なり、世帯単位で計算されます。
医療費控除
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が基準額を超える場合、税務署に確定申告をすることにより超えた分の医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付される制度です。
有料老人ホームに入居している場合、月額利用料に対しては医療費控除を受けられませんが、日々消費するおむつ代や、訪問診療などで医療機関にかかった費用は医療費控除の対象になります。
おむつ代の控除を受ける場合は、医師に「おむつ使用証明書」を書いてもらう必要があり、紙おむつの使用が本人にとって不可欠な医療行為であると認められた場合は医療費控除の対象となります。
確定申告を行う際、還付の請求をする時は添付書類として領収書も提出しなければならないので、
必ず保管しておきましょう。
おわりに
今回は有料老人ホームの種類や入居に関する費用や流れなどについて解説いたしました。
有料老人ホームを検討されている方の中には、特養の入居申請はしていても順番待ちで現在は入居できない、といった理由で有料老人ホームを選択される方もおられるのではないかと思いますが、有料老人ホームの需要は近年の高齢化社会に伴い、今後も増加傾向が続くことが見込まれています。
また、有料老人ホームへの入居を希望する方々のライフスタイルは様々で、アクティブな生活を求める方や介護やリハビリを通じて自立を目指す方、静かで穏やかな生活を望む方など、人それぞれに求めるスタイルは違います。
このようなニーズに応えるため、有料老人ホームはそれぞれに異なる設備やサービス内容を充実させています。将来を見据えて、個々のライフスタイルや身体状況に相応しいケアやサービスを提供し、快適なシニアライフを過ごすことができる施設を慎重に選びたいものです。
トピックス【介護サービスが必要になったら】記事のご案内
過去の記事をまとめております。よろしければご参照ください。
参考リンク
厚生労働省
公益財団法人 長寿科学振興財団 健康長寿ネット
https://www.tyojyu.or.jp/net/kaigo-seido/shisetsu-service/yu-home.html