【介護サービスが必要になったら】介護の豆知識その⑩~介護に疲れていませんか?介護疲れの原因と対処法について~
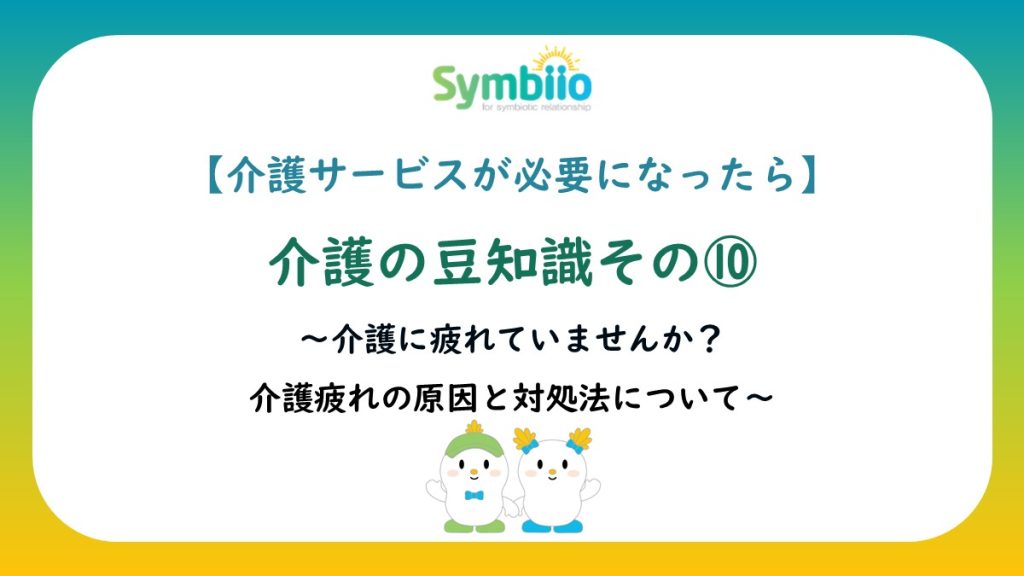
はじめに
大切な家族が要介護状態になってしまったら、精神的なショックはもちろんのこと、まず何から始めればよいのか分からない戸惑いから、パニックに陥る方も多くおられます。
さらに仕事にも私生活にも影響を及ぼす可能性があり、介護を始める当初から大きな精神的・肉体的な負担がかかることも多々あります。
特に在宅での介護は24時間365日続くため、介護者の多くが「介護疲れ」を経験しますが、この介護疲れが蓄積すると、介護うつなどの深刻な問題に発展する場合があります。
介護疲れは介護を行うすべての人に共通する問題で、特別なことではありません。
そのような時は一人で抱え込まず、誰かに相談するだけでも気持ちが軽くなりますし、また、外部のサービスを利用して介護の負担を軽減することもできます。
本記事では、介護疲れの原因や介護疲れを軽減させるためのポイントについて解説いたします。
介護疲れを引き起こす3つの負担
介護疲れは主に身体的、精神的、経済的理由による3つの負担から生じます。
1.身体的な負担
在宅介護では起き上がりや体位変換・移動・衣服の着替え・トイレや入浴の介助などを行います。
これらの介助は介護者にとって腰や膝、腕に過度な負荷をかける要因となり、特に女性や高齢者が行う場合、体力的な負担は一層大きくなります。
また日中の介護活動に加えてトイレ介助やおむつ交換が必要になると、夜間に起きる必要が生じ、
十分な睡眠を確保できないことが多くなります。
2.精神的な負担
在宅介護は身体的な疲労だけでなく、精神的にも大きな負担がかかります。
特に同居家族が介護対象者の病状に理解を示さず協力が得られないと、介護者は家庭内で孤独感を抱え、悩みを他者に話すことができなくなります。
さらに認知症の方の介護では意思疎通が難しいことなどから、精神的負担がより増してしまいます。
介護の終わりが見えないことによる不安や疲労は、介護者に深刻な影響を及ぼす可能性があり、特に精神的な負担が大きいことは外見から判断しにくいため、介護者自身やその周囲の人々がこの状態に気づき、解消に向けた行動を取ることが重要です。
3.経済的な負担
公的介護保険制度だけでは介護にかかる全ての費用をカバーすることはできません。
介護保険サービスを利用する場合でも、紙オムツなどの介護用品は別途費用が発生します。
また、介護と仕事を両立させることが難しくなり、仕事を辞めることになると収入が減少するため、
経済的な不安が増す場合があります。
介護疲れが引き起こす問題とは?
在宅での介護が始まると、介護疲れがさまざまな問題を引き起こすことがあり、介護うつ、介護離職、介護放棄(ネグレクト)といった深刻な問題が発生することがあります。
1.介護うつ
介護うつは、介護による様々な要因の負担が重なり、介護疲れが蓄積することで発症するうつ病です。
この状態になると食欲不振や睡眠障害、疲労感、焦燥感、思考障害などの症状が現れ、介護ができなくなるだけでなく、生活や健康にも深刻な影響を及ぼすことがあります。
※介護うつについては次章「介護の豆知識その⑪~介護うつとは?セルフチェックで予防しよう~」
にて詳しくご説明いたします。
2.介護離職
介護離職とは、介護と仕事の両立が難しくなり、介護のために仕事を辞めることを指します。
介護離職は介護者の収入が減少して経済的な負担が増すことや、社会的な孤立を引き起こす可能性があります。介護離職を防ぐためには、働きながら介護ができる体制を整えることが重要です。
3.介護放棄
介護放棄(ネグレクト)は、要介護者の世話を怠り、放置する状態を指します。
介護者が疲れ果てると、食事や入浴の介助、医療機関への受診、排泄ケアなどを放棄してしまうこともあり、このような介護放棄を防ぐためには、介護疲労を軽減するためのレスパイトケアや、適切な介護サービスの利用が重要になります。
介護疲れを軽減する方法
介護疲れは、その要因を減らすことで対処することができます。
計画をする際には、自分のライフスタイルをできるだけ変えない方法を考えましょう。
例えば、介護保険サービス、介護保険外サービス(自費サービス)、行政サービスの3つの高齢者支援サービスを効果的に組み合わせることで、介護の負担を軽減することが可能です。また、外部のサポートを受けることもおすすめです。
1.介護保険が適用されるサポート
①訪問介護
②訪問入浴介護
③デイサービス
④ショートステイ
この他にも様々な介護保険サービスがございます。
これらのサービスを利用するためには、介護保険の申請が必要です。
申請に関しては、お住まいの市区町村の窓口や地域包括センターにご相談のうえ、ご家庭に合ったサービスを選んでみてください。
2.介護保険適用外のサポート(自費)
配食サービス
家事代行サービス
送迎サービスなど
3.行政によるサービス
緊急通報サービス
理美容サービス
おむつサービスなど
(市区町村によって、助成内容は異なります)
4.専門家や自助グループによるサポート
①ケアマネジャー
普段から悩みを相談することで様々なアドバイスを受けられるだけでなく、介護者や要介護者に適したケアプランの変更や介護保険サービスの提案も受けられます。
②地域包括支援センター
地域包括支援センターの専門家、例えば保健師やケアマネジャーには無料で相談することできるため、担当のケアマネジャーに話しにくい場合は、こちらを利用する方法もあります。
③介護家族の会
介護者同士で在宅介護の悩みや思いを打ち明けることで、同じ境遇の者同士でしか得られない共感や安心感を共有することができ、さらに経験者からのアドバイスや有用な情報も得られ、悩みの解決に繋がることがあります。
都道府県や市区町村、NPO法人などが主催する「家族のつどい」などの場もあり、お住まいの地域包括センターに問い合わせるか、インターネットで情報を探してみてください。
④その他
介護者にとって地域とのつながりは非常に重要です。
特に認知症の介護を行っている場合、町内会や民生委員、マンションの管理人、交番、行きつけのお店など、周囲の人々に状況を説明し、声掛けをしておくとよいでしょう。
5.介護施設への入居という選択肢も
近年では介護施設が「第二の自宅」としての重要な役割を果たし、利用者が安心して生活できる環境が整えられています。介護施設に対する抵抗がある方でも、見学や入居体験を通して価値観が変わる方も多く見られます。
介護が必要になった際、要介護者とその介護者の両方が安心して暮らすことが最も大切です。
そのためには、年齢を重ねて介護が必要になる前や在宅介護に限界を感じる前に、介護施設について色々と調べておくことも大切になってきます。
介護疲れを軽減する心とからだのケア
介護による不安や疲れを軽減するためにはストレスがたまる前に対策することが非常に大切です。
以下のような対応を心がけてみてはいかがでしょうか。
1.リラックスできる時間を意識的に作る
自分が「気持ちが良い・心地良い」と感じる時間を意識的に作ることが心身の癒しにつながります。
アロマオイルや入浴剤を使ってリラックスしたり、心地よい音楽を聴くことで気分のリフレッシュをはかることや、マッサージグッズを利用して疲れを癒すこと、好きな映画やドラマを観るなど楽しみを見つけることも効果的です。読書に没頭することも、心の安らぎをもたらします。
2.レスパイトケア
介護サービスは介護を受ける方だけではなく、介護をしている方が休息を取るためにも利用することができます。
こうした介護者を支援するサービスを「レスパイトケア」と言い、介護を要する障がい者や高齢者の家族が一時的に介護から解放されるように、代理の機関や公的サービスなどを利用して、日頃の心身の疲れを回復させることができます。
※詳しくはトピックス記事「介護の豆知識その④~レスパイトケアとは?利用目的と効果について~」にて解説しております。
3.とにかく一人で頑張りすぎない!
介護に対する真摯な姿勢は大切ですが、過度な責任感や完璧主義はご自身の心と身体に大きな負担をかけることにつながります。
介護は一人で抱え込まず、同居する家族や兄弟・姉妹と役割分担をし、協力体制を築くことが非常に大切です。また家族間の協力だけでなく、介護サービスなど外部の支援を積極的に活用することも、在宅での介護を続けていくには重要な要素になります。
4.介護のスキルを学ぶ
介護のスキルを学ぶことによって介護の負担が軽減されることは多く、特に移動介助や排せつ介助のコツを知ることで、介護がよりスムーズに行えるようになります。
介護の専門スキルは自治体が開催している介護教室などで習得することができます。興味のある方は、お住まいの自治体に問い合わせのうえ、参加可能な教室で体験してみてはいかかでしょうか。
おわりに
介護疲れは、介護を行う方々にとって共通の問題です。
介護に追われる日々が続くと、介護者自身の健康が損なわれる可能性が非常に高くなります。
そのような状態を避けるためには、週に一度デイサービスを利用したり、不安に感じていることを誰かに話すなど、一人で抱え込まずに少しでも周囲に頼り、介護サービスを上手に利用して、ご自身が休める時間をしっかりと確保することがとても大切です。
また時間ができた際には、自分の好きなことを楽しんだり、友人と過ごしたり、運動をしてストレスを解消するなど、自分の時間を大切にするよう心がけてみましょう。
介護が必要になった時、もしくは日々の介護生活で困り事があった時、そしてお疲れがたまった時、
これまでのニュースルームの介護関連トピックスを少しでもご参考にしていただけると幸いです。
トピックス【介護サービスが必要になったら】記事のご案内
過去の記事をまとめてございます。よろしければご参照ください。
参考リンク
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001236476.pdf
公益財団法人 長寿科学振興財団
https://www.tyojyu.or.jp/kankoubutsu/gyoseki/ninchisho-yobo-care/h30-5-1.html
https://www.tyojyu.or.jp/kankoubutsu/gyoseki/ninchisho-yobo-care/h30-5-10.html