【介護サービスが必要になったら】介護の豆知識その①~地域包括支援センターとは?~
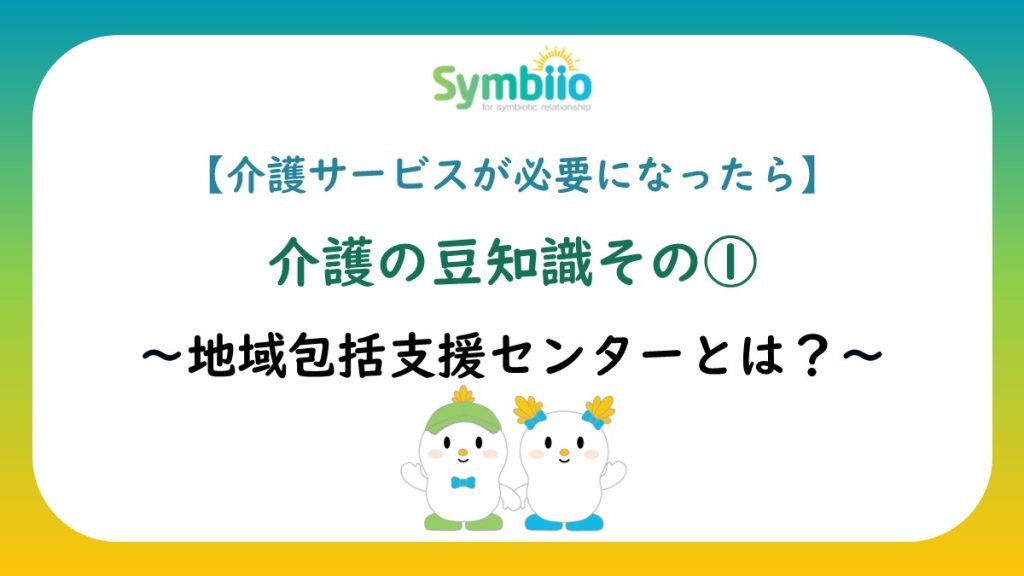
はじめに
今回のトピックスより「介護の豆知識」シリーズを掲載させていただくこととなりました。
介護関連の話題の中で、耳にしたことはあるけれど、意味や違いがよく分からないワードやトピックスを深掘りし、知っていると役に立つ豆知識としてご紹介させていただきます。
第一回目のテーマは「地域包括支援センター」についての解説となります。
ご自身やご家族に介護が必要になった際、まず何から始めたら良いのか分からない方も多いのではないでしょうか。
そんな時は地域の高齢者やそのご家族に向けた介護に関する情報提供や相談支援を行っている地域包括支援センターの活用をおすすめします。
本記事では、この地域包括支援センターが具体的にどのような所で、どのような相談ができるのかについて解説いたします。
地域包括支援センターとは?
地域包括支援センターは対象地域の高齢者の健康や生活全般に関する相談支援を行う地域密着型の総合相談窓口です。
各市区町村に設置された地域包括支援センターは高齢者やそのご家族、支援者が利用できるようになっており、日常生活の心配事から病気、介護、金銭的な問題や虐待まで、多岐にわたった相談を受け付けています。
このセンターでは多様な相談内容に対応するために保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャー(主任介護支援専門員)などの専門スタッフが配置されており、地域に住む高齢者に関わることなら何でも相談できるようになっています。
利用の条件
地域包括支援センターの対象地域に住んでいる65歳以上の高齢者の方が利用することができます。
地域包括支援センターは一般的に、介護予防や介護支援を必要とする高齢者のための地域支援・サービス拠点といったイメージで、市町村ごとに1カ所以上設けられており、公立中学校の学区を基準にエリア分けされているケースが大半です。
地域包括支援センターの役割
地域包括支援センターでは、主に4つの業務を行っています。
①総合相談・支援
高齢者の健康や生活、介護に関する悩みや相談を幅広く受け付けています。
要介護や要支援認定の申請方法や介護保険サービスの利用手続きについての詳しい案内など、相談内容に応じて専門スタッフが必要なサービスを選び、紹介することで、高齢者の支援につなげています。
②介護予防ケアマネジメント
要支援1・2と認定された方や、今後支援や介護が必要になる可能性のある方に対して、介護予防のための支援を行います。
具体的には、介護予防ケアプランの作成、介護予防サービスの案内や以下のような内容が含まれます。
- ・歩行の状態や交通機関を使えるか、などの移動範囲・移動能力
- ・家庭生活を含む日常生活の状態
- ・社会参加、対人関係、コミュニケーション
- ・健康管理・精神面(うつ、認知症等)
ほかにも高齢者の介護予防を目的とした運動サークルや活動が実施されているケースもあり、参加者の健康維持や介護予防を目的として、将来的な介護の必要性を軽減することにつなげています。
③権利擁護
地域で安心して生活するために、高齢者の権利に関する相談を受け付けています。
具体的には消費者被害に関する相談や対応、虐待の早期発見とその対応、さらに判断能力の低下により金銭管理が難しくなった高齢者に対して、金銭的搾取や詐欺から身を守るための成年後見制度活用のサポートなどを行っています。
④包括的・継続的ケアマネジメント支援
高齢者にとって暮らしやすい環境にするために、地域全体の医療・保健・介護分野の専門家から地域住民までの幅広いネットワークをつくり、そこで暮らす高齢者の課題解決や調整を行っています。
具体的な取り組みとしては、地域ケア会議の開催や、ケアマネジャーへの個別相談・アドバイスなどが挙げられます。
また、支援が難しい事例に対しても指導やアドバイスを行い、自立支援型ケアマネジメントのサポートを行っています。
どのような相談ができる?
地域包括支援センターでは高齢者自身からの相談だけではなく、その家族や友人、近所の方からの相談も受け付けています。
高齢者は何かトラブルを抱えていたとしても、まだまだ大丈夫と自分の力を過信していたり、他人に頼ることは迷惑をかけることだと考えて誰にも相談せずに困窮するケースが多いため、周囲の人々の気づきが大変重要になってきます。
些細なことでも「おかしいな」と感じたら、相談してみましょう。
以下はその一例です。
- ・最近親の物忘れが激しく、認知症かもしれないと思っている
- ・最近体調が思わしくないが、かかりつけ医がいない。どこへ受診すればいい?
- ・要介護認定はどうやって受けたらいい?
- ・介護保険を使って家を改修したい。どうすればいい?
- ・介護予防のプログラムが受けたいので紹介してほしい
- ・成年後見人制度について教えてほしい
困り事が漠然としていて、はっきり説明できない場合でも問題ありません。
具体的な問題が分からなくても、職員が相談者の状況を整理し、必要なサポートを一緒に考えてくれますので、気兼ねなく安心して窓口を利用することができます。
相談は無料
地域包括支援センターでの相談は無料受けられますが、紹介されたサービスを利用する際には費用が発生する場合があります。
例えば「誰に相談すればよいか分からない」「介護についての理解が不足している」「親の様子が変だと感じる」など、「こんなこと相談してもいいのかな?」といった些細な事でも、まずは気軽に問い合わせてみましょう。
地域包括支援センターを構成する専門家
地域包括支援センターでは、保健師(看護師)・社会福祉士・主任ケアマネジャーの3職種の方々が、それぞれの専門性を活かして連携しながら、専門分野のみにとらわれずに最善策を出し合い、問題解決に向けた対応を行っています。
①保健師(看護師)
主な担当:介護予防マネジメント
業務内容:予防給付、介護予防事業のプラン作成。要介護状態への予防、身体状況悪化防止
②社会福祉士
主な担当:総合相談・支援、高齢者の権利擁護事業
業務内容:住民の各種相談対応、高齢者に対する虐待防止・早期発見、その他権利擁護
③主任ケアマネジャー
主な担当:包括的・継続的マネジメント
業務内容:地域ケア会議の開催、ケアマネジャーの相談・助言、支援困難事例等への指導・助言など
地域包括支援センターを活用しよう!
地域包括支援センターは、対象となる高齢者が住んでいる地域に基づいて担当センターが決まります。
初めて利用する際は、まず地域の自治体に問い合わせて、自分の担当センターの情報を確認することが重要です。
センターに相談する場合は予約が必要なこともあるため、事前に確認しておくと安心です。また、状況によってはスタッフが訪問してくれることもあります。
地域包括支援センターは地域によって名称が異なることがあるため、詳しい情報は自治体のホームページなどで確認することをおすすめします。
健康な状態の時でも、将来の困りごとに備えて地域包括支援センターの存在を知っておくことで、いざという時に慌てずに対応できるようになります。
おわりに
地域包括支援センターを上手に活用することで、介護が必要になる前の段階から、早期に対策を講じることが可能です。
介護について困った時の相談や、将来的に起こりうる問題に対して備えることができますので、介護に関する不安や疑問がある場合は、地域包括支援センターに相談してみましょう。
トピックス【介護サービスが必要になったら】記事のご案内
過去の記事をまとめております。よろしければご参照ください。
参考リンク
厚生労働省
公益財団法人 長寿科学振興財団 健康長寿ネット
https://www.tyojyu.or.jp/net/kaigo-seido/chiiki-shien/houkatsu.html