【介護サービスが必要になったら】介護の豆知識その⑥~介護リフォームとは?(前編)補助金対象の工事や申請方法について~
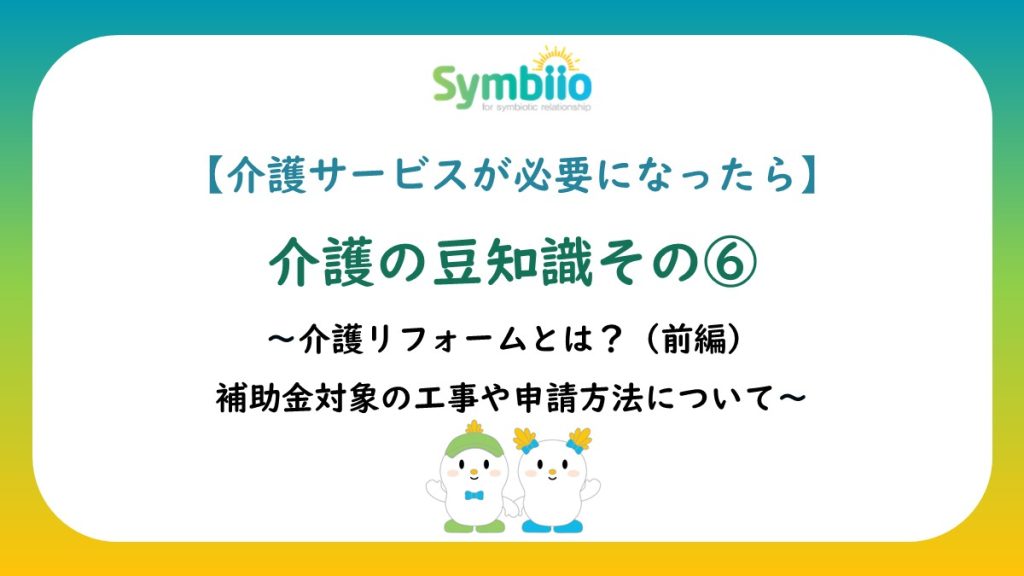
はじめに
ご自宅での介護が必要になってきた際、生活面での安全性を考えて、介護リフォームを検討される方も多いのではないかと思います。
身体状況に応じたリフォームをすることによって、自宅での転倒や怪我のリスクを減らし、要介護者が自分の足で移動する意欲や自立心を高めることも期待できます。
また、一定の条件を満たすことで、公的介護保険から住宅改修(介護リフォーム)費が支給される制度もあります。
本記事では、公的介護保険による住宅改修費の支給要件や支給額、対象となるリフォーム内容などについて解説いたします。
→過去記事「介護保険の基礎知識⑥~介護保険を利用した住宅改修について~」も併せてご参照ください
介護リフォームとは?
介護リフォームとは、介護や支援が必要な高齢者の暮らしをより安全なものにするためのリフォーム(住宅改修)のことです。住み慣れた家をリフォームをすることで、安心して生活を続けることにもつながります。
介護リフォームのタイミング
怪我や病気で病院から退院した後、自宅で安全に生活するために介護リフォームを行うケースが多くみられます。
また、年齢とともに運動機能が低下すると、廊下のちょっとした段差でつまづいたり、階段から転落したりするなど、自宅内での事故が起こる可能性が高まります。
介護リフォームは日常生活が不便になってから行うのではなく、要支援・要介護認定を受けた際には早めに利用を始めることも大切になってきます。
転倒は大きな怪我につながるリスクが高く、特に大腿骨の骨折や腰の悪化は寝たきりになる可能性を引き起こしますので、これらのリスクを軽減するためにも、介護リフォームを早めの段階で検討することをおすすめします。
介護リフォームには公的介護保険が適用される
要介護認定で要支援1以上に認定されると、介護リフォームに公的介護保険が適用されます。
公的介護保険における介護リフォームは「居宅介護住宅改修及び介護予防住宅改修」と呼ばれ、一定の条件を満たすことで改修費の一部が支給されます。
また、介護リフォームの費用を抑えるための制度として、介護保険の補助金と各市区町村による助成金の2つがあります。
介護保険の補助金を利用する
介護保険は40歳以上の方が加入することが義務付けられている制度で、要支援や要介護の認定を受けた場合に介護費用の一部を負担してもらえる仕組みです。
そして介護のための住宅改修費も介護保険から支援を受けることができるため、介護リフォームにかかる費用を抑えることが可能となり、住宅改修費の自己負担は介護保険制度に基づき1割から3割の範囲で設定されています。
支給条件を満たすと20万円を上限として支給され、20万円を超過した部分については全額自己負担になります。
基本的には利用者がいったん工費を全額支払い、その後に申請を行うことで保険者である市区町村から工費の介護保険自己負担割に合わせて介護リフォーム料金の7~9割が支給されます。1割負担の場合、20万円の支給のうち2万円は自己負担となり、最高18万円が支給される制度で、実質的には1割から3割の自己負担で済むことになります。
また、引っ越しをしたり、要介護区分が3段階以上上昇した場合には、再度支給を受けることが可能です。
自治体によっては事前申請を行うことで、利用者が自己負担額のみを施工業者に支払い、残りを自治体が直接施工業者に支払う受領委任払い方式を採用している場合もあります。必要に応じて、事前に自治体に問い合わせることをおすすめします。
公的介護保険における住宅改修費の支給限度基準額は前述のとおり、利用者1人につき20万円です。
この金額は1回のリフォームで使い切る必要はなく、複数回に分けて利用することが可能です。
例えば、最初のリフォームで5万円を支給された場合、次回に15万円の工事を行うこともできます。
介護リフォームの補助金の支給要件
公的介護保険における住宅改修費(介護リフォームの補助金)が支給される要件は以下の通りです。
1.制度の利用者が要介護認定で要支援1・2、要介護1~5のどれかに認定されていること
2.制度の利用者が介護保険被保険者証に記された住所に住んでいること
3.介護リフォームを行う住宅の住所と利用者の介護保険被保険者証の住所が同じであること
4.現在、制度の利用者が介護施設や病院などに入所・入院していないこと
5.改修費が支給されるのは一人1回、工費は20万円まで
(利用者だけでなく、住宅についても1つの住宅につき原則1回まで)
6.原則として過去に上限額まで住宅改修補助金の支給を受けていないこと
介護保険で対応できる工事内容
公的介護保険では住宅改修費として介護リフォームの補助金支給の対象となる工事があらかじめ定められています。
支給対象となる工事の種類は以下の通りです。
1.手すりの取り付け
転倒防止や移動、立ち座りなどの動作をしやすくすることが目的で、玄関や廊下、浴室、トイレなどや、段差のある場所に手すりを固定する工事です。
2.段差の解消
具体的にはスロープの設置や床のかさ上げ、敷居を低くする方法が含まれます。住宅内の段差を解消することは転倒防止につながるだけではなく、特に車いすユーザーにとって利便性が向上します。
例えば、玄関の土間からフローリングへの段差を低くすることで、車いすでの移動が可能になります。
3.滑り止めなど床材の材料の変更
転倒防止のために、既存の床材や通路面の材料を滑りにくい材質に変更する工事にも補助金が支給されます。また、車いすの利用を考慮して、畳の床をフローリングに変更する工事も対象となります。
ただし、極端に滑りが悪い状態になると、逆に転倒のリスクが高まるため、注意しましょう。
4.扉の取り替え
握力の低下でドアノブを回すのが難しい場合や車いすでの移動で開き戸が障害となる場合には、扉を引き戸に変更するリフォームも補助金の対象となります。また、重くて開けにくい引き戸を軽量で開けやすいものに取り換える工事も補助金の対象です。
5.便器を洋式便器などに取り換え
和式便器から洋式便器への交換や、暖房便座や洗浄機能がついた便器への交換も住宅改修費支給の対象となります。また、既存の洋式便器を利用者の使い勝手に合わせて、立ち上がりやすい高さに調整したり、向きを変更したりすることも支給対象に含まれています。
6.上記のリフォームのために必要な工事
上記5つのリフォームにともなう工事も制度の対象となっています。
例えば、手すりを取り付けるための下地工事や浴室の床のかさ上げにともなう給排水設備工事、スロープ設置にともなう転落・脱輪防止のための柵、扉を取り付けるために壁や柱を補強する工事や、便器の取り換えに必要な給排水設備工事なども改修工事として認められます。
介護リフォーム補助金の申請方法
住宅改修費で介護リフォームを行うためには、以下のような流れで申請・手続きを行います。
1.要介護、あるいは要支援の認定を受ける
2.ケアマネジャーに相談する
3.施工業者が作成する見積、工事図面などを確認し、契約する
4.自治体に申請書類のうち、事前申請に必要な書類を提出
5.事前申請の審査結果を確認
6.介護リフォームが実施される
7.施工業者に工事費を支払う
8.自治体に住宅改修費の支給を申請する
9.住宅改修費が支給される(工費の7~9割)
申請に必要な書類
申請は着工前後の2回必要です。
住宅改修理由書はケアマネジャーなどの資格を持つ人が作成しなければなりません。
また、領収書の写しを提出する際には原本の提示が求められます。
これらのポイントを押さえておきましょう。
・住宅改修内容について記載した書類
・改修する場所や費用の見積などを記入した申請書
・写真など、改修前の住宅の状況が確認できるもの
・ケアマネジャーが作成する住宅改修理由書
・施工業者の作成した工事図面、工事費見積書
・領収書
・工事費内訳書
・住宅所有者の承諾書
・写真や図面など、改修後の状態が確認できるもの
支給方法の種類
公的介護保険における住宅改修費の支給方法には主に「償還払い」と「受領委任払い」の2つがあります。
償還払いでは、利用者が施工業者に工事費を全額支払った後、自治体から補助金が支給されるため、一時的に自己負担が必要です。
一方、受領委任払いは事前に申請することで利用可能になります。この支払い方法では、利用者は自己負担分のみを施工業者に支払い、残りの金額は自治体が直接業者に支払います。受領委任払いを希望する場合は、制度を申請する前に自治体に詳細を確認しておきましょう。
おわりに
今回は介護が必要になった際の住宅改修について、補助金の対象要件や工事内容についてお話させていただきました。
高齢になっても暮らしやすい環境を整えるために、身体状況に合わせた介護リフォームは今後どのご家庭でも必要になってくるものではありますが、ご自宅の状況や工事が必要な場所によっては時間も費用も要しますので、早めの段階で計画を進めていくことが大切になります。費用の面や工事と申請の流れを念頭に置きながら、しっかりとしたリフォーム計画を検討していきましょう。
次回の後編では工事費用の目安、各市区町村の助成金で介護リフォームをする場合の概要や介護リフォームの注意点などについて解説させていただきます。
次回もどうぞよろしくお願いいたします。
トピックス【介護サービスが必要になったら】記事のご案内
過去の記事をまとめてございます。よろしければご参照ください。
参考リンク
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001016043.pdf
公益財団法人 長寿科学振興財団 健康長寿ネット
https://www.tyojyu.or.jp/net/kaigo-seido/kaigo-service/kaishu-hi.html