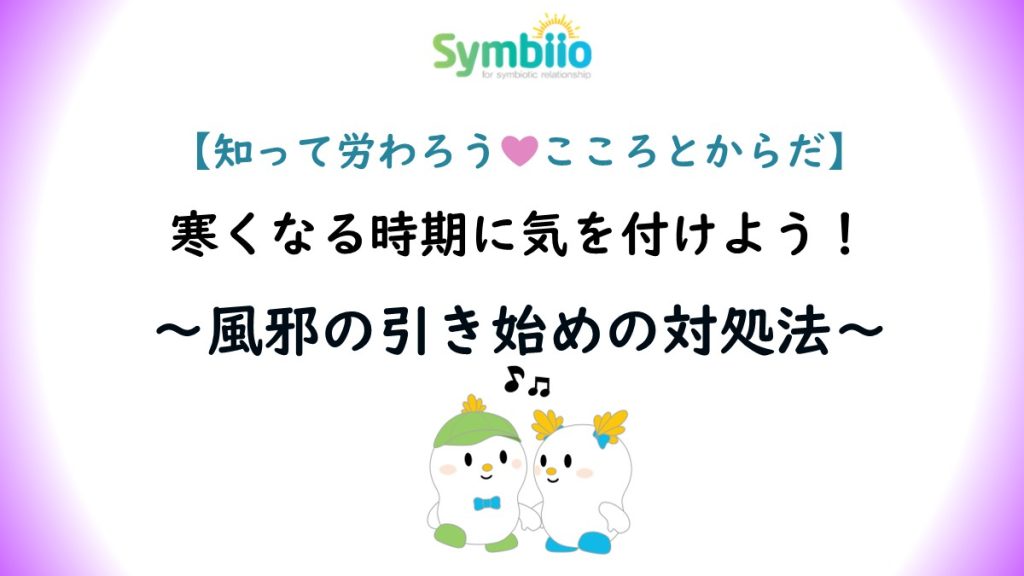
季節が進んで気温が下がってくる頃、急にのどが痛くなったり鼻水が出たりすると、「もしかして風邪かな?」と思う方が多いと思います。
風邪は安静にしていれば治る病気ですが、軽視して普段通りの生活を続けていると、回復が遅れたり、症状が悪化することがあるため、引き始め時の対処がとても重要になります。そこで今回は風邪の初期症状と、風邪の引き始めの頃にできる対処法についてご紹介いたします。
「風邪」とは正式な病名ではなく、上気道の急性炎症や発熱、倦怠感などを伴った全身症状を指す総称・俗称であり、正式な名称は「風邪症候群」「感冒」「急性上気道炎」などです。風邪の主な症状は、のどの痛み、鼻水、咳、場合によっては発熱、頭痛、全身倦怠感、食欲不振などを伴います。
風邪の主な原因はウイルス感染によるもので、約200種類以上のウイルスがあるといわれています。そのため、一度風邪をひいて免疫ができても、そのほかの異なるウイルスや変異したウイルスに再度感染することもあります。さらに体調が悪く免疫力が低下している場合は、細菌による気管支炎や肺炎などの二次感染のリスクが高くなるため、体調が回復しにくい、症状が長引いていると感じた場合は、早めに医療機関を受診してください。
- ・くしゃみ、鼻水、鼻づまり
- ・のどの痛み
- ・咳、たん
- ・発熱、寒気がする
- ・頭痛、筋肉や関節の痛み
- ・全身の倦怠感
ウイルスが鼻や口から体内に侵入すると、まず鼻腔内や口腔内、のどなどに付着して炎症を引き起こします。この過程でウイルスが増殖していくと、呼吸器の免疫防御機能が体内に侵入した「異物」であるウイルスを排出しようと反応するため、咳やたん、鼻水、くしゃみが出たり、粘膜内部に炎症が起きて喉の痛みや鼻づまりといった呼吸器症状が現れることがあります。これらの症状が見られた場合、風邪の引き始めの可能性があるため、症状の変化に注意をしながら、体をしっかり休めて回復に努めることが大事です。
風邪の主な感染経路は、大きく分けて飛沫感染と接触感染の二つです。
飛沫感染は感染者が咳やくしゃみをした際にウイルスが空気中に放出され、それを吸い込むことで感染します。一方で、接触感染は感染者の手や感染者の触れたドアノブ、つり革、共有した物などに付着したウイルスが体内に入り、感染します。
また、生活習慣の乱れや疲労、寝不足などにより体力が低下すると、風邪を引きやすくなります。さらに、人と近距離で会話する機会が多いことや、家や職場の空気が乾燥していることもウイルス感染の一因となります。
十分な睡眠をとること
風邪による咳や発熱の症状があると、体がウイルスと戦うために免疫機能が活発になりエネルギーを使うため、ご自身が思っている以上に体力を消耗します。風邪を少しでも早く治すためには、安静にすることが非常に大事です。普段よりも長い睡眠時間を確保し、良質な睡眠をとることを心がけ、体力を回復させましょう。
体を温めること
風邪の引き始めには発熱や悪寒、震えといった全身症状が現れることがあります。発熱は体がウイルスの増殖を抑えて排除するための自然な反応です。そのため、発熱を無理に抑えてしまうとウイルスの排出が遅くなるため、熱が上がりきるまで体を温めましょう。熱が下がり始めたら、体内に熱がこもらないよう心地よい程度に冷やし、熱を逃がすようにすると良いでしょう。不快に感じる場合は無理に冷やす必要はありません。その時の体調に応じて快適に過ごせるよう、適切に対処することが大切です。
こまめな水分補給
発熱すると発汗や呼吸数が増えることで、体内の水分や塩分が大量に失われてしまいます。発熱による脱水症状を防ぐために、こまめに水分を補給しましょう。体が冷えないように常温の水やスポーツドリンク、経口補水液などをこまめに少しずつ摂取するとよいでしょう。
消化の良い食事で栄養補給
体力や免疫機能を高めるためには、栄養バランスの整った食事が重要ですが、体力をつけようと肉類など高カロリーのものや高脂質の食事を摂ると、消化に負担をかける場合があります。食欲がない時には胃に優しく、水分と栄養を同時に摂取できて、体を温める効果もある消化の良いおかゆやスープ、味噌汁などがよいでしょう。
部屋を加湿すること
風邪を引いてしまった後でも、室内の加湿はとても重要です。のどや鼻の粘膜には「繊毛(せんもう)」があり、ウイルスを排除する役割を果たしていますが、乾燥するとその働きが低下します。加湿器を使ったり、濡れたタオルを室内に掛けて、乾燥を防ぎましょう。
風邪とインフルエンザの主な違いは、症状の現れ方とその重症度にあります。
風邪は比較的ゆっくりと進行するのに対してインフルエンザは進行が早く、風邪の諸症状に加えて38℃以上の高熱や強い倦怠感、関節痛、筋肉痛などの全身症状が急速に現れるのが特徴です。風邪を引いた時より症状が重いと感じた場合や持病がある場合、季節性のインフルエンザが周囲で流行し、疑わしい場合は必ず医療機関を受診しましょう。また、医療機関を受診する際は周囲への感染拡大を防ぐために、事前に電話で連絡し、指示に従って行動しましょう。
睡眠不足や過労は免疫力を低下させてしまうため、風邪を引きやすくなってしまいます。質の良い睡眠で疲労を回復させ、規則正しい生活を送ることで自律神経を整え、体調管理に日々気を配ることが風邪のウイルスを遠ざけることにつながっていきます。そしてバランスの取れた食事や適度な運動をすること、普段から体を冷やさないようにすることなど、免疫力を高める生活習慣を心がけましょう。
さらに帰宅したらすぐに感染症予防の基本である手洗い・うがいを励行し、人混みの中や乾燥しやすい時期、季節性の感染症が流行する時期などはマスクを着用し、飛沫感染を防ぎましょう。
また、慢性的なストレスは自律神経を乱し、免疫細胞の働きを抑制しダメージを与えるストレスホルモンを過剰に分泌させます。そのため、ストレスが強い状態が続くと免疫力が低下して、様々な感染症にかかりやすくなってしまいます。風邪に負けない体を作るためには、ストレスをためないように心のケアを欠かさないことも非常に大切です。
風邪を長引かせないためには、風邪の引き始めのサインを見逃さないことが重要です。体調に少しでも異変を感じたら、安静にして休息を取り、決して無理をせずに自分の体を大切にしましょう。
風邪の一般的な症状の多くは、およそ1週間で回復に向かいます。しかし、症状が長引く場合や、普段の風邪と異なる症状(高熱が続く、鼻水の異臭、しつこく重い咳が続く、のどの腫れや痛みがひどい、など)が見られる場合は、単なる風邪ではなく他の病気や二次感染、細菌感染のサインかもしれません。すみやかに医療機関を受診し、治療を受けるようにしましょう。