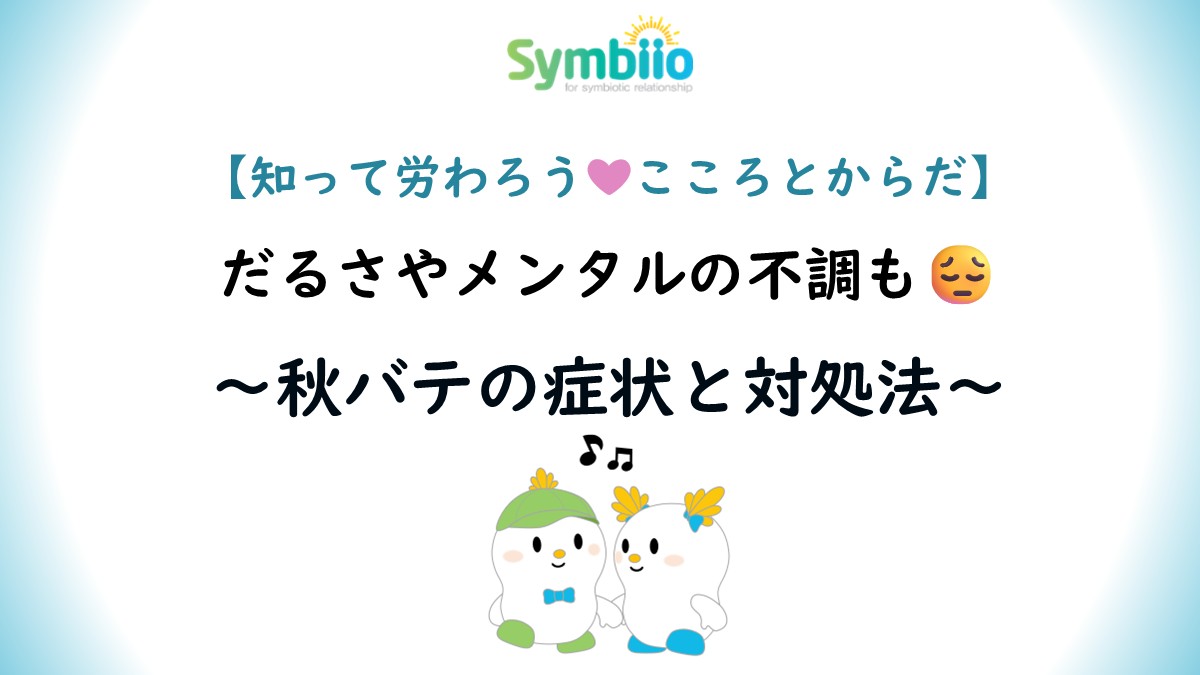
秋になると涼しさを感じる一方で、体がだるく疲れやすいと感じる方が増えるそうです。
これは「秋バテ」と呼ばれ、季節の変わり目特有の体調不良です。医学的に明確な定義はないものの、夏の疲れや昼夜の寒暖差が大きくなることが原因とされています。特に近年の猛暑から急激に気温が変化する秋は、体がその変化に適応しきれず、疲労感や様々な心身の不調を引き起こすことがあります。
今回は秋バテの原因や症状、対策について解説いたします。
自律神経の乱れ
秋バテの主な原因は自律神経の乱れからくるものです。
季節の変わり目は一日の間でも寒暖差が大きく、急激な気温の変化が交互に訪れるため、環境が不安定になりやすいです。このような変化によって自律神経の調整がうまくいかなくなり、その結果、身体的・精神的な不調が引き起こされることがあります。
気温・気圧の変化
「女心と秋の空」という言葉があるように、秋は天候が変わりやすく、特に雨の日が多くなることで、気分や体調に影響を及ぼすことがあります。
秋は昼夜の寒暖差が大きくなるだけでなく、台風や低気圧などで気圧の変動も激しくなります。そして気温や気圧の変化に対応するために交感神経が優位になると、いつも以上にエネルギー消費が増加して、疲れやだるさといった症状が現れることがあります。
夏の疲労の蓄積
連日の暑さが夏の疲れを引き起こし、秋になるとその影響が表面化することがあります。
夏の暑さや冷房による寒暖差が体に疲労を蓄積させてしまい、この疲労が回復しないまま秋を迎えると、秋バテのリスクが高まります。
生活習慣の乱れ
冷房による冷えや熱帯夜による睡眠不足などの生活習慣があると、免疫力が低下し、風邪などの感染症にかかりやすくなります。特に秋は気温の変化が大きく、免疫力が低下していると体調を崩しやすくなります。また、冷たい麺類などの簡単な食事が多くなると栄養が偏り、体調を崩す原因にもなります。
だるさ・疲労感
秋バテの代表的な症状には、だるさや疲れやすさが挙げられます。
秋になると日照時間が短くなることによってセロトニンが不足し、体が重く感じたり、エネルギーが湧かないといった症状が現れることがあります。またこのような症状に伴って、よく眠れない、寝付けないといった睡眠障害が生じることもあります。
頭痛や肩こり・胃腸の不調
気温の変化によって自律神経が乱れると血行が悪くなることがあり、頭痛や肩こり、首のこりといった症状が現れやすくなります。
また、夏の間に冷たい食べ物を多くとっていると、胃腸が冷えて消化機能が低下し、食欲不振や胃の不快感、さらには下痢や便秘といった消化器系の問題が生じることがあります。特に食欲が低下すると十分な栄養を摂取できず、結果として疲労や倦怠感が増すという悪循環が生じることがあります。
精神的な不調
気温の変化によって気分も不安定になり、やる気が出なかったり、憂鬱な気分になるなどのメンタル不調が見られることがあります。また、自律神経の乱れが原因でイライラや憂鬱な気分が強まることもありますが、これには気温の変化に加えて、日照時間の減少も関わっているとされています。
規則正しい生活を
規則正しい生活を心がけることで、自律神経を整えることができます。
具体的には、毎日同じ時間に寝起きし、朝・昼・夜の食事をきちんととることが大切です。また、早寝早起きを意識し、十分な睡眠を確保することで体力を回復させることができます。
体を冷やさないこと
急に冷え込むことが多い時期は、身体を冷やさないことが重要です。特に首まわりの太い頸動脈が冷えると血流が滞りやすくなるため、ネックウォーマーやスカーフ、マフラーを使って温めることで、血液が温まり全身の血流が改善される効果が期待できます。
また、冷たい食べものを避け、体を内側から温める食事を心がけましょう。内臓が冷えると胃腸の不調などが起こりやすくなるだけでなく、免疫力が低下してしまいます。食事には根菜類やショウガなどの体を温める食材を使い、血行を良くしましょう。他にもスープやお鍋、温かいお茶などを積極的にとりいれ、内臓を冷やさないようにすることが大切です。
さらに夜は入浴して体を温めるようにしましょう。40℃程度のぬるめのお湯に浸かると副交感神経が優位になり、眠りにつきやすくなります。
適度な運動をしよう
秋は気温が下がって涼しく過ごしやすくなり、運動に適した季節です。
軽いウォーキングやストレッチなど無理なく体を動かすことで血行を促進することができ、冷えや疲労感を軽減する効果が期待できます。また、運動は自律神経を整えることにつながり、気分転換にも効果的です。
バランスのとれた食事を意識する
栄養バランスがとれた食事をとるようにしましょう。体の基本的な構成要素の一つであるたんぱく質は、内臓や血液、筋肉などの機能を維持する働きがあるため、不足すると代謝も悪化し、体の機能が正常に働かなくなることがあります。そのため、肉、魚、乳製品、大豆、卵などの良質なたんぱく質を朝昼晩しっかりと摂取しましょう。
さらに、疲労回復にはビタミンB1の摂取も重要です。ビタミンB1は糖質をエネルギーに変える役割を果たし、豚肉やレバー、紅サケ、玄米、さつまいも、ほうれん草、豆腐などに多く含まれています。また、腸内環境を整えるために発酵食品や食物繊維の摂取も意識しましょう。柔らかく煮た野菜の汁物などは、食物繊維を多く含み消化にも良くおすすめです。
水分補給を心がける
秋でも水分補給は非常に重要です。私たちは日常生活の中で、1日に約2.5リットルほどの水分を失っています。食事や体内で補われる水分は約1.3リットルほどなので、水を全く飲まないと1.2リットルほど不足してしまいます。そのため、1日あたり1.5リットルを目安に水分をとりましょう。
また、カフェインを含む飲み物は利尿作用があるため、水分補給には水や白湯、麦茶などが適しています。内臓を冷やさないために、常温または温かい飲み物を意識してとりましょう。
夏から秋への季節の変わり目に感じる体調不良や疲労感は「秋バテ」による症状の可能性が高く、主な原因としては、気温の急激な変化、冷房による体の冷え、そして夏の疲れの蓄積などが挙げられます。
秋バテを予防・解消するためには、温かい食事をとること、適度な運動、入浴でのリラックス、規則正しい生活が重要です。
秋は心地よく過ごせる季節である一方で、気温の変動が大きく不安定で、体に負担がかかりやすい時期でもあります。上記の対策を日常生活に取り入れることで自律神経を整え、季節の変わり目でも快適に過ごせるように心がけてみましょう😊