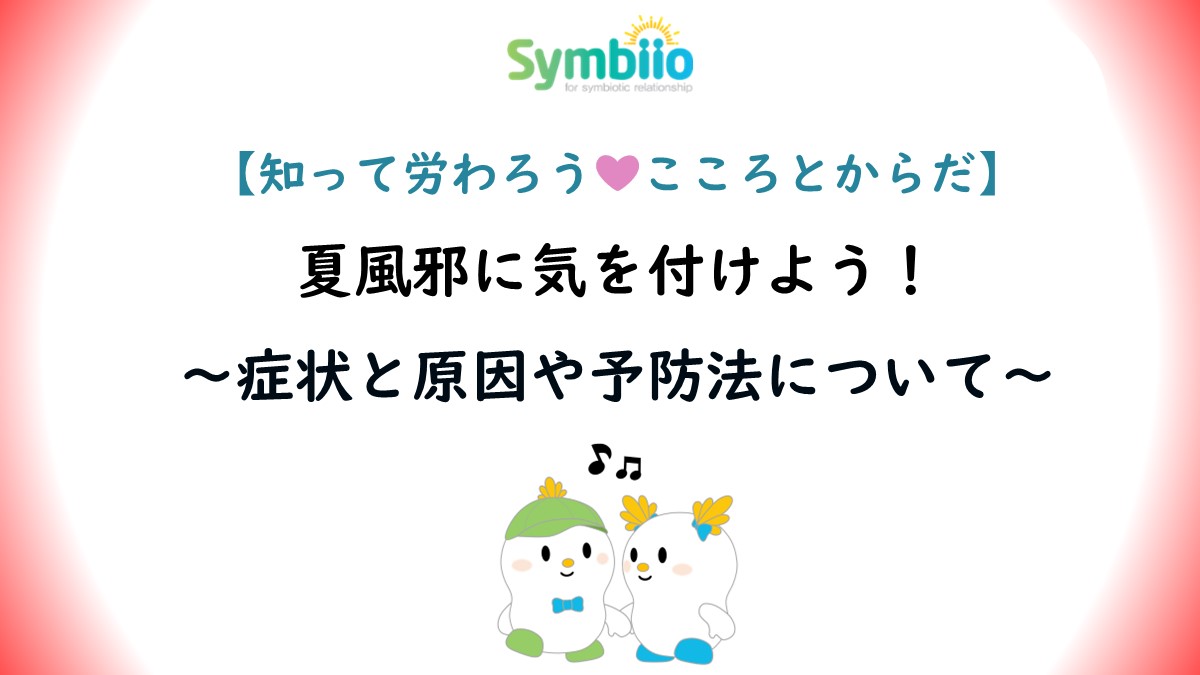
毎年6月~8月に流行する夏風邪。エアコンの普及により快適な室温が保たれる一方で、体の冷やし過ぎによって自律神経のバランスが崩れ、免疫力が低下して様々な体調不良を引き起こしたり、夏風邪のウイルスに感染しやすくなってしまいます。今回はこの時期に特に気を付けるべき夏風邪の症状や原因、予防法についてご紹介いたします。
夏風邪とは夏場にかかるウイルス感染症のことで、冬場とは原因となるウイルスが異なります。
夏風邪は冬場の風邪よりも軽症で済むように思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実際は症状やウイルスの性質、その対処法に大きな違いがあります。そのため、冬の風邪と同じ対処をすると症状が悪化したり、別の病気を引き起こす可能性もあるそうです。
一般的に、冬場に流行する風邪のウイルスは低温で乾燥した環境を好みますが、夏風邪のウイルスは高温多湿を好むため、湿度が50%を超えると活発になり、毎年梅雨の6月頃から増加し始め、7月にピークを迎える傾向にあります。風邪の原因とされるものはウイルスだけではないですが、約90%はウイルスによるものとされているそうです。
夏場に流行するウイルスの代表がエンテロウイルスやアデノウイルスです。
エンテロ(腸)、アデノ(喉)※というように、発熱に加えて腹痛や下痢、喉の痛みなどが特徴的な症状です。夏風邪が「おなかにきやすい」とされる理由は、主にエンテロウイルスが腸内で増殖するため、様々な胃腸症状が引き起こされます。
※エンテロとアデノ
「エンテロ」はギリシャ語の「enteron(腸)」に由来し、医学用語では「腸・腸管」を意味し、「アデノ」は元々体内の分泌・排泄器官を指す「腺」という意味で、特に扁桃腺やリンパ腺を指す言葉です。
ヘルパンギーナ
ヘルパンギーナは夏場、主に乳幼児の間で流行するウイルス性の感染症で、発熱と共に口腔内や喉の奥に痛みを伴う小さな水疱や潰瘍ができることが特徴です。感染者の咳やくしゃみ、唾液を通じて飛沫感染し、水疱や感染者の便に触れることでも経口・接触感染します。
手足口病
手足口病は主に5歳以下の乳児を中心として夏に流行します。手、足、口に水疱性の発疹を引き起こし、大人も感染することがあります。感染経路は主に飛沫感染、経口感染、接触感染です。
ヘルパンギーナと手足口病は、エンテロウイルスによって引き起こされます。特徴の一つとして、口内に水ぶくれ(水疱)ができます。また、ウイルスが腸管内で増殖することで胃腸炎の症状が現れることもあり、「おなかの風邪」と呼ばれることもあります。
プール熱(咽頭結膜熱)
小さな子供を中心に流行し、高熱や喉の痛み、結膜炎の3つの症状が特徴のウイルス感染症です。
かつてはプールでの集団感染が多く見られ、プール利用時の感染者との接触やタオル等の貸し借りによって感染拡大したことから「プール熱」と呼ばれてきました。感染の原因はアデノウイルスで、主な感染経路は感染者の咳やくしゃみによる飛沫感染、または感染者が触れた物に付着したウイルスが手を介して口や眼の粘膜から入る経口感染や接触感染です。
夏風邪は主に小さい子どもがかかりやすい病気ですが、大人も感染することがあります。
最近では大人の発症例が増加しており、大人が夏風邪にかかると子どもに比べて重症化するリスクが高いとされています。特に、小さな子どもと接する機会が多い方や子どもがいる家庭内では感染のリスクが高まるため、注意が必要です。
夏風邪の原因となるウイルスは主に腸内で増殖し、体外に排出されるまでに時間がかかります。
夏は暑さによる疲労や食欲不振、エアコンでの冷えなどにより体力や免疫力が低下しやすく、さらにウイルス感染には抗生物質が効かないため、ウイルスを体内から排出するまでに時間を要してしまいます。これらの要因が重なることで、夏風邪の回復が遅れ、症状が長引いてしまうことが多いそうです。
高温の発熱は熱中症と夏風邪の共通症状ですが、両者には違いがあります。
熱中症は体温調節機能が失われ、42℃を超える高体温が持続、または上昇しますが、熱中症は体温が高いままであるのに対し、夏風邪は体温が1日の中で変動します。
熱中症特有の症状には、意識障害や手足のしびれや動かしにくさ、40℃以上の発熱にもかかわらず汗が出ない、などです。一方で、体温の上下変動や咳、鼻水、咽頭痛、発疹などの感冒症状(風邪の症状)がある場合は、夏風邪である可能性が高いです。
冷房の温度・冷やしすぎに注意!
エアコンを長時間使用すると体が冷えすぎて免疫力が低下することがあり、また、おなかを冷やしてしまうと腸の働きが悪くなることがあります。
自宅では冷えすぎないようエアコンの温度設定に注意し、エアコンを時々止めて換気をしたり、会社などでは長袖や腹巻を着用することで体の冷えを防ぎましょう。
うがい・手洗いは必須
冬の風邪は主に咳やくしゃみによる飛沫感染が原因で広がります。一方、夏風邪は経口感染によるものが多く、感染した手で鼻や口を触ることで広がるため、予防にはこまめな手洗いやうがいが重要です。特に、トイレや洗面所でのタオルの使いまわしは避けましょう。湿って汚れたタオルはウイルスが繁殖しやすいため、清潔なタオルを使用しましょう。
しっかり体調を整えよう
夏バテを防ぎ、体調をしっかりと整えることも夏風邪の予防には重要です。
暑さによって倦怠感や疲労感が増すと、食欲が減退して免疫力を維持するための栄養が不足しがちになります。また、疲労が自律神経に影響を与えると、病気への抵抗力が落ちてウイルスに感染しやすくなってしまいます。特に睡眠不足は体調に大きな影響を及ぼすため、夜間十分に眠れていないと感じたら、昼寝を取り入れるとよいでしょう。仕事がある方でも、15分程度の昼寝でリフレッシュ効果が得られますので、ぜひ試してみてください。
免疫力を高める栄養素を取り入れよう
風邪予防には、栄養バランスの取れた食事が大切です。特に夏風邪に対抗するためには、抗酸化作用のあるビタミンCや粘膜を強化するビタミンA、体の組織を作るたんぱく質を意識的にとりましょう。
食欲がない時には、チーズやヨーグルトなどの乳製品で動物性たんぱく質を補うとよいでしょう。これらの乳製品には免疫を活性化する成分が豊富に含まれています。また、ショウガやニンニクを使った料理は免疫力を高める効果があり、夏の体力維持には最適です。
市販の風邪薬は、夏風邪に伴う発熱や鼻水、咳などの不快な症状を和らげる効果が期待できます。
発熱がある際には市販の鎮痛解熱剤や一般的な風邪薬を使用すると思いますが、風邪の症状に腹痛や下痢が伴う場合は注意が必要です。市販薬の中には胃腸に負担がかかるタイプの成分が入っている場合があり、特に下痢症状はウイルスを排出する作用があるため、風邪薬や下痢止めを使用してしまうと体内のウイルスの排出が遅れてしまい、症状が長引く可能性があります。さらに胃腸炎や下痢を起こすと脱水症状にもなりやすいので、必ず水分は多めにとりましょう。
腹痛や下痢が続き、症状が重い場合は市販薬で様子を見ずに、早めに医療機関を受診して適切な薬を処方してもらいましょう。また、喉の腫れや痛みがひどく、飲み物が通りにくい場合も早期の受診が必要です。夏風邪は38〜40℃の高熱が2~3日続くことがあり、無理に汗をかいて解熱しようと布団をしっかりとかぶる方もおられると思いますが、悪寒が無い場合は熱がこもって逆効果となり、無駄に体力を消耗してしまいます。ただでさえ夏場は暑さから体力を消耗しやすいため、体調不良を感じたら水分と塩分を十分に摂取して脱水症状を防ぎ、しっかりと睡眠をとって回復を図りましょう。
夏風邪は初期症状を夏バテと勘違いしてしまうことが多く、対処が遅れて症状が長引いてしまうこともあります。
夏バテを防いで体調管理に気を配る事は夏風邪の予防にもつながり、冷房の使いすぎや冷たい飲食物で体を冷やし過ぎてしまうことも冷房病や夏風邪の一因となるため、暑い時期こそ生活環境と体調を整えておくことはとても大切です。
また、近年では夏場でもインフルエンザが流行したり、ノロウイルスや食中毒などの重症化する病気にも注意が必要です。風邪やウイルスを寄せ付けないためには、日ごろから手洗い・うがいを習慣化し、体調管理と共に免疫力を高めて、しっかりと予防していきましょう。