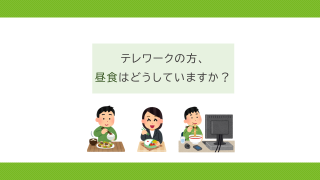メゾン・シンビーオ(在宅就労の豆知識部屋)
関東のお漬物をご紹介
こんにちは、本記事では関東地方のお漬物をご紹介します。
東京
小松菜キムチ
小松菜を漬け込んで作るキムチで、ほろ苦い小松菜の味わいとみずみずしい口当たりが特徴です。
国産の原料を使用し、輸入キムチと同じ発酵技術で作られているものもあります。
小松菜は葉物野菜の中でもアクが少なく食べやすく、栄養価も高い野菜です。
べったら漬け
東京の漬物といったらこちら、大根を塩で下漬けし、米麹や砂糖で漬け込んだ甘口の漬物です。
江戸時代から東京で親しまれており、東京日本橋の宝田恵比寿神社で毎年10月に開催される「べったら市」の名物としても有名です。
東京たくあん
大根の美味しさを引き出したあっさりとした味付けの沢庵(たくあん)で、コクやキレがあり、爽やかな味で箸休めにピッタリの漬物です。
神奈川
ひょうたん漬け
小型のひょうたんをしば漬けにしたもので、縁起物としてお祝いの席などで出されます。
※ひょうたんは、食用ひょうたんというウリ科の植物の実を漬物にしたものです。
薄く剥いて干した「干瓢(かんぴょう)」と同じ植物で、
ベトナム産のひょうたんを原料としており、苦味がなく、産毛が生えている5cm以内くらいの若く小さいうちに収穫されます。
ふすま漬け
三浦半島の特産加工品で、小麦精麦の副産物であるふすまを使ったダイコンの漬物です。
桜の花漬け
桜の花を塩と梅酢に漬けたもので、秦野市や小田原市が主産地です。
千葉
鉄砲漬け
千葉県成田地域や香取市を中心に伝わる漬物です。
うりの種子をくり抜いてしその葉で巻いた青唐辛子を詰めみ、無添加醤油やみりんを主体とした調味液で漬け込みます。
穴をあけた瓜が砲筒、青唐辛子が弾のようだということで鉄砲漬けという名前がつけられました。
らっきょう田舎漬け
らっきょうを酢や砂糖、塩などのシンプルな調味料で漬け込んだ食品で、らっきょうの食感が楽しめます。
らっきょうは中国のヒマラヤ地方原産で、日本には平安時代に渡来し、食用や薬用として栽培されてきました。
埼玉
深谷ねぎしば漬け
埼玉ブランドの深谷ねぎを使った漬物で、さっぱりとした梅酢風味シバ漬けのピンク色がキレイで、ネギとキュウリの食感が楽しいお漬物です。
ほとんどニオイがしませんので、お弁当の付け合わせにいかがでしょうか?
しゃくし菜漬け
秩父地方に伝わる漬物で、塩だけでなく乳酸発酵も利用して漬けられる点や、塩分控えめで酸味がある点が特徴の逸品です。
しゃくし菜とはアブラナ科の植物で、チンゲンサイの仲間である「雪白大菜(セッパクタイサイ)」を漬けたものです。
秩父地方では、タイサイの形がしゃもじに似ていることから「しゃくし菜」と呼ばれています。
群馬
群馬焼ねぎちびっこ胡瓜味噌
小さなキュウリがたくさん入った甘味噌がおいしいきゅうりの味噌漬けで、味噌の中に刻んだ下仁田ネギも入っています。
胡瓜の歯ごたえが楽しく、味は青唐辛子も入っていますが、全体的に甘い味噌味ですので、洗わずに味噌ごと一緒にどうぞ。
ご飯やお酒のお供にいかがでしょうか。
きゅうり生姜
きゅうりと生姜をほんのり甘い漬け込み液に漬けたお漬物で、シャキッとしたきゅうりと生姜の風味がよく合い、歯ごたえも楽しめます。
物によっては梅干しエキスで漬け込んだものもあるそうです。
鮮度が大事な漬物のようですが、ご飯によく合うようですのでぜひいかがでしょうか。
茨城
ごさい漬け
大根とサンマ(イワシやサケを使うこともある)を塩と唐辛子で自然発酵させた郷土料理です。
鹿島灘沿岸地域(鉾田市・鹿嶋市など)に伝わり、以前はサンマが揚がる時期に保存食として漬けられていました。
練梅たくあん
梅とたくあんを組み合わせた水戸名物で、梅のほど良い酸味とたくあんのパリパリとした食感が特徴です。
栃木
たまり漬け
味噌の製造過程でできる副産物である「たまり」に野菜を漬け込んで作られる栃木県日光名物の漬物です。
保存性に優れており、野菜本来の味や香りが濃縮されています。
歯ごたえがあり、たまりの風味が特徴の逸品です。
にらねっこ
栃木県産のニラを本醸造しょうゆで漬け込んだお漬物で、シャキシャキ食感と香りや味を活かしており、お漬物だけでなく料理の素材や薬味としても活用できます。
それではまた。

私は視覚と聴覚に障害があり、視覚障害については何も見えていません。
当事者の一人として、皆様に白杖や点字ブロック以外のことも知っていただけたらと思い、視覚障害者が利用しているツールについてご紹介していこうと考えています。
皆さま、どうぞよろしくお願い致します。