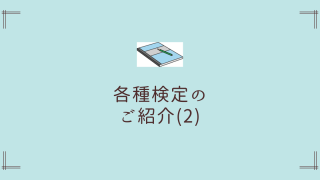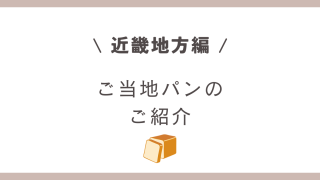メゾン・シンビーオ(在宅就労の豆知識部屋)
関東のお雑煮
栃木
地域によって多少の違いはあるものの、全体的に「具だくさんで食べ応えのある醤油ベースのすまし汁」という共通点があります。
栃木県県央エリアのお雑煮
- 特徴:けんちん汁風
- 味わい:醤油ベースのすまし汁
- 餅:角餅
- 具材:地元産の野菜、鶏肉、紅白なると、かまぼこ、三つ葉など
日光エリアのお雑煮
- 特徴:揚げ餅を特長とする「竜頭風お雑煮」
- 具材:肉や野菜
地元の食材、例えば山菜などが使われることもあります。
茨城
茨城県のお雑煮は、地域や家庭によって様々なアレンジがあるため、一概に「これ!」とは言えません。
※茨城は納豆のイメージが強いですが、茨城県では、お雑煮に納豆は入れません。
他の地方では納豆を入れる地域もあります。
茨城県県北エリアのお雑煮
- 特徴:醤油ベースのすまし汁が一般的で、具材に鶏肉や地元産の野菜をたっぷり入れる
- 餅:焼いた角餅
→一部地域では、豆腐をすり潰して出汁でのばし、砂糖で甘く味付けした「白和え雑煮」というお雑煮も食べられている
県西エリアのお雑煮
- 関東風のお雑煮の特徴:出汁の風味を活かしたシンプルな味付け
- 味わい:醤油ベースのすまし汁
- 餅:焼いた角餅
- 白和え雑煮の味わい:豆腐の風味と砂糖の甘さが合わさった優しい味わい
- 特徴:豆腐をすりつぶして昆布だしと砂糖で味を付ける
埼玉
埼玉のお雑煮は、地域によって様々な特色があり、家庭ごとに味付けや具材が異なることもあります。
太郎兵衛もちのお雑煮
越谷の四丁野村の名主、会田太郎兵衛が栽培したもち米を使ったお雑煮で、特徴は次の通りです。
- 餅:太郎兵衛もち
→コシが強く粘り気がある
- 具材:鶏肉、小松菜、大根、人参、やつがしら(里芋の一種)など
- 味わい:醤油味のすまし汁仕立て
県北エリアのお雑煮
- 特徴:関東風の醤油味のすまし汁仕立てが一般的
- 具材:鶏肉、しいたけ、青菜など
- 出汁:干し椎茸の戻し汁
- 地域性:出汁や具材にスルメを利用する地域もある
秩父 地方のお雑煮
- 特徴:シンプルながらも素材の味を生かした昔ながらの味わい
- 味:カツオ出汁の醤油味
- 具材:鶏肉、大根、ゴボウ、ニンジン、サトイモ、ネギ、キノコなど
- 餅:焼いた角餅
群馬
中毛(ちゅうもう)地域のお雑煮
地域に根付いた独特の味わいと調理法で、お正月には欠かせない郷土料理です。
- 味わい:けんちん汁風
- ベース:かつお節や昆布のだし
具座具材:角餅、※「つと豆腐」※
※わらで包んで煮た豆腐
→煮崩れしにくく、味が染み込みやすい
東毛(とうもう)地域のお雑煮
- 特徴:シンプルながらも素材の味を生かした、飽きのこない味わい
- 味わい:醤油ベースのすまし汁
- 餅:角餅
- 具材:多く入れ過ぎず、鶏肉、人参、大根、三つ葉などの具材をシンプルに組み合わせる
- 出汁:昆布とかつお節鶏
→肉のだしを加えることもある。
西毛(せいもう)地域のお雑煮
- 味わい:醤油ベースのすまし汁
- 餅:角餅
- 具材:大根、人参、里芋、鶏肉、油揚げ、こんにゃくなど
→地域によっては、お麩やなると、三つ葉などを加えることもある
東京
都区部(23区)のお雑煮
出汁:鶏出汁
- 味わい:すまし汁仕立て
- 餅:焼いた角餅
- 具材:鶏肉、小松菜、かまぼこなど
→みつばやゆずの皮を添えることもある
多摩地域のお雑煮
- 具材:鶏肉と小松菜
- 味わい:醤油ベースのすまし汁
- 餅:焼いた角餅
島嶼部(とうしょぶ)のお雑煮
地域ごとに様々なバリエーションがあり、それぞれの個性を楽しむことができます。
- 出汁:かつお節と昆布
- 具材:鶏肉、小松菜、里芋、人参、大根、なると、焼き麩など
神奈川
特定の統一された形式があるわけではなく、地域ごと、さらには家庭ごとに多様な特徴が見られます。
神奈川県全体のお雑煮の傾向は以下の通りです。
- 餅:角餅
- 味わい:醤油ベースの澄まし汁
- 具材:鶏肉、かまぼこ、ほうれん草や小松菜など
千葉
関東風のすまし汁が基本ですが、特に「はばのり」という海藻を使うのが大きな特徴です。
地域によってはさらに異なる特色が見られます。
全体的な特徴としては次の通りです。
- 出汁:かつお出汁ベースのすまし汁
- 餅:焼いた角餅
- 具材:鶏肉、小松菜、かまぼこ、しいたけなど
九十九里・南房総(房総)地方の「はば雑煮」
- 出汁:かつお出汁のすまし汁
- 具材:※はばのり※、青のり
※房州産の海藻で、炙ってから手でもんで細かくし、お椀に盛ったお雑煮の上にたっぷりと振りかける
→独特の磯の香りと、昆布に近いような食感が特徴です。
→鶏肉、小松菜、人参、かまぼこなどが入ることもある
- 特徴:「一年中、幅を利かせられる」という縁起担ぎで食べられる
→海苔を大量にかけるのが特徴で、汁を覆い尽くすほど乗せることもある
* 特に山武郡市(九十九里地域)や市原市でこの習慣が強く見られます。
北総地方(内陸部)
- 出汁:かつお出汁のすまし汁
風習:三陸の「切り昆布」を使う習慣が残っている場所もある
→佐原地域では、仙台藩との交流があったため
- 具材:芋(特に八頭)、大根、人参などの地元の野菜
→それらをふんだんに使う具だくさんな「けんちん仕立て」に近いお雑煮も見られる
- 餅:焼いた角餅
- 特徴:海の幸である「はばのり」の代わりに、地元の畑で採れる野菜や加工品が使われる傾向がある
→内陸部であるため
* 「鏡大根」や「太陽を表す人参」など、縁起を担いだ切り方をすることも。
その他の地域(東葛飾、千葉・市原など)
これらの地域は東京都心に近いため、より一般的な関東風のお雑煮に近い傾向があります。
- 出汁: かつお出汁のすまし汁
- 具材: 鶏肉、小松菜、かまぼこ、しいたけなど、シンプルな具材
- 特徴:地域全体で「はばのり」が浸透しているわけではなく、家庭によって入れるかどうかが異なる
「あおさ」をかける家庭も多く見られます。
以上

私は視覚と聴覚に障害があり、視覚障害については全盲です。
当事者の一人として、皆様に白杖や点字ブロック以外のことも知っていただけたらと思い、視覚障害者が利用しているツールについてご紹介していこうと考えています。
皆さま、どうぞよろしくお願い致します。