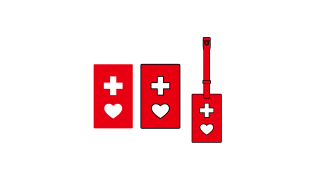メゾン・シンビーオ(在宅就労の豆知識部屋)
関西のお雑煮
こんにちは、本記事では近畿地方各県のお雑煮の特徴をご紹介します。
滋賀
地域や家庭によって特色が見られます。
湖北地方と湖南・湖西地方で、多く見られる傾向をご紹介します。
湖北地方(長浜市、米原市など)
- 味わい:あっさりとした醤油ベースのすまし汁
- 出汁:かつお節と昆布
- 具材:大根、白菜、水菜、かまぼこ、鶏肉など
- 餅:丸餅を焼かずに、そのまま入れることが多い
湖南・湖西地方(大津市、草津市、甲賀市、高島市など)
- 味わい:まろやかで優しい味わい
- 出汁:昆布とかつお節でとった出汁に白味噌を溶き入れる
- 具材:大根、里芋(特に「頭芋」と呼ばれる親芋を使うことが多い)、人参など根菜類、家庭によっては鶏肉や三つ葉、糸かつおを飾ることもある
- 餅:丸餅を煮て柔らかくしてから入れることが多い
三重
中部地方と近畿地方それぞれの県に接しており、中部地方と近畿地方の文化が混在する特徴を持っています。
北勢、中勢、南勢、伊賀、東紀州の5つの地域それぞれのお雑煮についてご紹介します。
北勢地方(桑名市、四日市市、鈴鹿市、いなべ市など)
- 味わい:あっさりとした醤油ベースのすまし汁
- 出汁:かつお節と昆布
- 具材:ほうれん草や小松菜などの「正月菜」と呼ばれる青菜、かまぼこ、鶏肉など
- 餅:角餅を煮るか焼くかして入れる
中勢地方(津市、松阪市など)
- 味わい:濃厚な赤味噌の風味が特徴で、コクと甘みのある味わい
- 風習:大晦日に濃縮した味噌汁を作り置きし、正月三が日に薄めて食べるという地域もある
- 出汁:昆布やかつお節でとった出汁に、濃厚な赤味噌を溶き入れる
- 具材:大根、里芋(特に「頭芋」と呼ばれる親芋を使うことも)、豆腐など根菜類が中心
- 餅:角餅を煮て柔らかくしてから入れることが多い
南勢地方(伊勢市、鳥羽市、志摩市など)
- 味わい:あっさりとしたすまし汁
- 地域性:小豆の甘みが特徴のぜんざい風のお雑煮もある
- 出汁:かつお節と昆布
- 具材:大根、白菜、菜葉など
- 餅:丸餅を用いる地域が多いが、角餅のところもある
- 風習:鳥羽市の一部地域では、小豆汁仕立てのお雑煮を食べる
伊賀地方(伊賀市、名張市など)
- 出汁:北部はすまし汁 、 南部は味噌仕立て(赤味噌)
- 味わい:すまし汁の場合はあっさりとした醤油ベース、味噌仕立ての場合は濃厚な赤味噌の風味
- 風習:名張市や伊賀市南部では、お雑煮に入れた餅を別途用意したきな粉につけて食べる
- 具材:大根、里芋、豆腐
- 餅:「花びら餅」と呼ばれる、手のひらで薄く伸ばした丸餅を使うことが多い
東紀州地方(尾鷲市、熊野市など)
醤油とみりんをしっかりきかせた、香ばしいすまし汁の味わいが特徴です。
具材が豊富で、それぞれの素材の旨味が溶け込んでいます。
- 出汁:かつお節と昆布でとった出汁が一般的で、地域によっては煮干しや焼き鮎で出汁をとることもある
- 具材:鶏もも肉、しいたけ、小松菜、にんじん、三つ葉など
- 餅:角餅を用いることが多いが、「ねこ餅」と呼ばれる独自の餅を使う地域もある
和歌山
地域によって多様な特徴が見られます。すが、すまし汁や焼いた餅を使う地域もあります。
紀北(きほく)地域、紀中(きちゅう)地域、紀南(きなん)地域それぞれに多くみられる特徴をご紹介します。
紀北地域(和歌山市周辺)
- 味わい:白みそ仕立てが多く、あっさりとした出汁に真菜の風味が加わり、優しい味わい
- 出汁:かつお節をベースにしたあっさりとした出汁
- 具材:大根、里芋、人参などの根菜類が用いられます。真菜(まな)
真菜とは、和歌山市内に多く見られる葉野菜で、白菜の一種です。「名(菜)を上げる」という縁起担ぎの意味もあると言われています。
- 餅:丸餅で、焼かずに煮て入れることが多い
紀中地域(有田市、日高川町、みなべ町周辺)
- 出汁:えそ(かまぼこの材料にも使われる魚)や干した鮎、ふしこ(鰹節の削りカス)
- 具材:根菜類と、焼かずに入れる丸餅
- 味わい:えそで出汁を執る地域ではあっさり、干した鮎を使う地域では鮎の旨味が溶け込んだ濃厚な味わいに、ふしこを使う地域では、みそ汁仕立ての味わい
地域によって様々な特色が見られます。
きなこ餅を添えるそうです。
奈良
お雑煮そのものは、基本的には近畿地方の特色である白みそ仕立ての丸餅(焼かない)が主流ですが、地域固有の具材や出汁の取り方、味付けの工夫があります。
奈良盆地周辺(北部)、吉野地域(南部)それぞれに多く見られるお雑煮の特徴をご紹介します。
奈良盆地周辺(北部)
白みそ仕立てで、まろやかで優しい甘みが特徴です。
あっさりとした出汁と白みその組み合わせが、素材の味を引き立てます。
- 出汁:昆布と鰹節を合わせた、あっさりとした出汁
- 具材:大根、人参、里芋、きな粉餅(最も特徴的なのが、お雑煮に入れた丸餅を、お椀から取り出してきな粉をまぶして食べる)、地域によっては豆腐や油揚げ、頭芋(かしらいも)と呼ばれるそのままの形のサトイモや、刻んだスルメを入れることもある
吉野地域(南部)
白みそ仕立てが多いですが、地域によってはすまし汁仕立てのところもあります。
具だくさんで食べ応えがあります。
- 出汁:鰹節や昆布の他、鶏肉から出汁をとる場合もある
- 具材:高野豆腐、こんにゃく、鶏肉、ごぼう、しいたけ、焼かない丸餅
大阪
- 出汁:昆布出汁が基本で、地域によってはかつお出汁と合わせる
- 味わい:地域によって異なり、同じ昆布出しでも、あっさりとした味わいと砂糖のきいた甘めの味わいの物がある
かつお出しと合わせる地域は、昆布だしにコクが加わり、しっかりとした味わいになります。
- 餅:丸餅を使うことが多く、焼かずに入れるか焼いてから入れる
- 具材:大根、にんじん、里芋、鶏肉、豆腐もしくは焼き豆腐、地域によってはかまぼこ
京都
地域によって特色が大きく異なります。
京都市内
白味噌のまろやかな甘みと、とろりとした舌触りが特徴です。
上品で優しい味わいで、餅の柔らかさと相まって非常に食べやすいです。
甘口のお雑煮として知られています。
- 出汁:昆布と鰹節で丁寧にとられた出汁に、甘みのある白味噌を溶き入れる
- 具材:丸餅(焼かずにそのまま入れる)、海老芋(えびいも)、金時にんじん、大根、里芋、鶏肉地域や家庭によってかまぼこや小松菜
京都府北部(丹後・丹波地域)
京都府北部、特に丹後地方や丹波地方では、京都市内とは異なるお雑煮が見られます。
- 出汁:醤油ベースのすまし汁が多いく、昆布や鰹節の他に、鶏ガラなどから出汁をとることもある
- 具材:角餅を使うことが多いが、地域によっては丸餅を焼いて入れることもある
- 味わい:すっきりとした醤油味
都府南部(山城地域)
京都府南部、特に山城地域では、京都市内のお雑煮に近いものが多いですが、一部地域で独自の特色も見られます。
- 出汁: 基本的には白味噌ベース
- 具材: 丸餅を使用し、海老芋、金時にんじん、大根など
都市内のお雑煮に似た甘めの白味噌味ですが、地域や家庭によって微妙な違いがあります。
- 餅:都市内とその周辺では焼かない丸餅を使用することが多く、他の地域では焼いた角餅や丸餅を使用することがある
- 地域性:地内でも家庭によって細かな違いがある
京都府のお雑煮は、その多様性から日本の食文化の奥深さを感じさせるものと言えるでしょう。
兵庫
地域によって多様な特徴があります。
神戸・阪神、播磨、但馬、丹波、淡路島それぞれに多く見られるお雑煮の特徴をご紹介します。
神戸・阪神地域
薄味で上品なおぞうにです。
- 出汁:和風だし(昆布・かつお)
- 餅:丸餅または角餅
- 具材:鶏肉、みつば、かまぼこ
播磨地域
東部と西部で出し・具材・味わいが異なります。
- 西播磨:角餅、鶏肉、清澄な出汁
- 東播磨:丸餅、醤油味、具沢山
但馬地域
素朴で濃厚な味わいのお雑煮が特徴です。
- 出汁:鶏がらスープ
- 餅:角餅が多い
- 具材:鶏肉、野菜
丹波地域
- 出汁:野菜の旨味を活かした出汁
- 餅:丸餅
- 具材:地元野菜
淡路島
- 出汁:瀬戸内の海の幸を使用
- 餅:丸餅
- 具材:地元の魚介類
以上

私は視覚と聴覚に障害があり、視覚障害については全盲です。
当事者の一人として、皆様に白杖や点字ブロック以外のことも知っていただけたらと思い、視覚障害者が利用しているツールについてご紹介していこうと考えています。
皆さま、どうぞよろしくお願い致します。