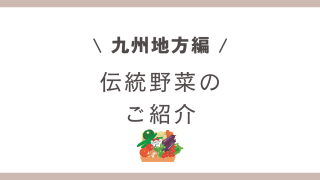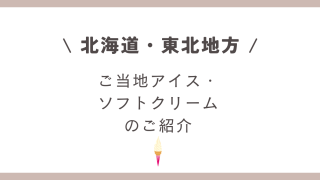メゾン・シンビーオ(在宅就労の豆知識部屋)
九州のお雑煮
こんにちは、本記事では九州地方各県のお雑煮をご紹介します。
福岡
博多雑煮
出汁は、焼きあご(トビウオ)から取った上品な出汁が特徴です。
昆布や干し椎茸を合わせることもあります。
具材は、出世魚であるブリと、福岡の伝統野菜であるかつお菜が欠かせません。
その他、大根、人参、椎茸など具だくさんで、縁起を担いで7種類の具材を串に刺しておく家庭もあります。
焼いた丸餅を使うことが多いです。
長崎
島原具雑煮
島原の乱の際に籠城した人々が餅と山海の幸を煮て食したのが始まりとされています。
具材は、鶏肉、アナゴ、シロナ、レンコン、ゴボウ、凍り豆腐、椎茸、卵焼き、丸もちなど、10種類以上の具材が入ることもあります。
佐賀
出汁は、スルメイカや昆布で取るのが特徴的です。
具材は、レンコン、人参、白菜など野菜が多く入ります。
出汁を取ったスルメイカを具材として入れることもあります。
丸餅を煮て柔らかくして入れます。
熊本
出汁は、かつおと昆布で出汁を取り、薄口醤油で味付けた澄まし汁が基本です。
具材は、「肥後京菜」「熊本長にんじん」「水前寺もやし」など、古くから栽培されてきた「ひご野菜」をふんだんに使う地域があります。
山鹿市周辺など一部地域では、砂糖を混ぜた納豆をお餅に絡めて食べる納豆雑煮もあります。
大分
地域によって特徴が異なります。
大分市内・竹田市周辺
麦味噌ベースの味噌汁にお餅を入れるのが特徴的です。
具材は、大分名産の椎茸は必須とされ、具材は比較的シンプルです。
国東半島エリア
甘口醤油仕立ての味付けが特徴で、あんこ入りの餅(あん餅)を入れるのが特徴です。
宮崎
出汁は、干し椎茸で取ることが多いです。
具材は「まめに働けるように」「長生きできるように」との願いを込めて、芽の長い豆もやし(水前寺もやしなど)を入れるのが特徴です。
鶏肉、里芋、ほうれん草などが入ります。
鹿児島
出汁は、特産物の殻付干し焼きエビや干し椎茸、昆布で取るのが特徴で、独特の香ばしい風味があります。
鹿児島の甘口醤油を使うことが多いです。
具材は、さつま揚げ、白菜、焼き豆腐、豆もやしなどが入ります。
九州では珍しく、焼いた切り餅(角餅)が使われる地域もあります
(島津家が江戸の文化を持ち帰った影響とも言われます)
沖縄
中身汁(なかみじる)
お雑煮ではありませんが、ご紹介します。
沖縄県の代表的な郷土料理の一つで、お正月や祝い事、法事などのハレの日に欠かせないお吸い物です。
「中身」とは、沖縄で食用とされる豚の内臓(大腸・小腸・胃など)のことを指します。
中身汁は、この豚の内臓を主たる具材とした澄まし汁です。
豚の内臓を使っているにもかかわらず、「脂っこそう」というイメージとは異なり、非常にあっさりとして上品な味わいが特徴です。
これは、豚の内臓に付着した脂や臭み、汚れを徹底的に取り除くため、小麦粉やおからで何度も揉み洗いし、繰り返し湯通し(茹でこぼし)するという、非常に手間のかかる丁寧な下処理を施すためです。
出汁は、かつお出汁と豚の内臓から出る豚出汁を合わせることで、旨味の相乗効果を生み出し、深みのある澄んだ出汁に仕上げます。
味付けは主に塩と醤油(薄口醤油)でシンプルに調えられます。
丁寧に下処理され、短冊状に切られた「中身」は、プニプニとした弾力のある独特の歯ごたえが楽しめます。
具材として他に、水で戻した干し椎茸やこんにゃくが入ることが多く、これらが異なる食感のアクセントになります。
風味を引き締め、さわやかな香りを加えるために、食べる直前におろし生姜(すりおろし生姜)や青ネギを添えるのが一般的です。
かつては、沖縄特有の香辛料であるヒハツ(島コショウ)を加えることもありました。
以上

私は視覚と聴覚に障害があり、視覚障害については全盲です。
当事者の一人として、皆様に白杖や点字ブロック以外のことも知っていただけたらと思い、視覚障害者が利用しているツールについてご紹介していこうと考えています。
皆さま、どうぞよろしくお願い致します。