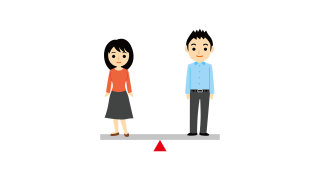メゾン・シンビーオ(在宅就労の豆知識部屋)
九州地方の伝統野菜
こんにちは、本記事では九州地方各県の伝統野菜をご紹介します。
大分
宗麟かぼちゃ(そうりんかぼちゃ)
日本最古のかぼちゃとされる伝統野菜で、大分県臼杵市で生産されています。
甘みが少なくねっとりとした食感が特徴で煮物、炒め物、揚げ物、蒸し物、スープ、お菓子などさまざまな料理に使用できます。
みとり豆
大分県宇佐市を中心とした県北部の地域で古くから栽培されているササゲの一種で、サヤは食べずに実だけを採るため「みとり」と呼ばれています。
小豆ほどの大きさで、黒色または赤色、腎臓形をしています。
大きさは同程度ですが、小豆と比べると色が黒くて硬く、風味も異なります。
小豆より作りやすく収穫しやすいという特徴があり、仏事や初盆、宇佐神宮の夏祭りのご馳走としても作られます。
みとり豆を使った「みとりおこわ」という料理があり、地元の人はこれを「おこわ」や「赤飯」と呼んできました。
そのほかにも、みとり豆の餡でまんじゅうやゆでもちが、お供え物として作られています。
沖縄
フーチバー
沖縄の方言でヨモギを指す言葉で、薬草や野菜として古くから活用されてきました。
ニシヨモギというヨモギの一種で、県外のヨモギとは異なり苦味が少ないほか、葉が大きく、独特のさわやかな香りがあります。
ビタミンA、カルシウム、カリウム、鉄分などの栄養素も豊富に詰まっています。
沖縄そばの薬味や沖縄風炊き込みご飯「ジューシー」の定番具材として使われているそうです。
天ぷらにしてカリッとした食感と独特の苦みを楽しむこともでき、他にも薬用茶や入浴剤として利用されています。
ハンダマ
沖縄本島での呼び名で、キク科の多年草であるスイゼンジナ(水前寺菜)の別名です。
葉の裏が鮮やかな赤紫色をしており、鉄分やビタミンA、ポリフェノールなどを豊富に含んでいます。
加熱するとヌメリが出て、茹でて和え物や雑炊、汁の具にするとほんのり紫に色づきます。
おひたし、サラダ、炒め物、天ぷらや漬け物として利用されています。
老化防止、免疫力向上、眼精疲労の改善などの効果があるとされており、血圧上昇を抑える効果がある事も分かっています。
鹿児島
さつま大長レイシ
鹿児島県の在来種で、果長が35~40cmの長形をしたニガウリ(苦瓜)の一種です。
果皮は鮮緑色で、果肉はかためで歯ごたえがあります。
栄養価が高く、風味や食味に優れています。
主に炒め料理や酢の物などに利用され、沖縄や南九州では豚肉との油炒めが有名です。
ゴーヤーチャンプルーなどの油炒めやジュース、酢漬などにもピッタリです。
山川大根
鹿児島県で生産される大根で、郷土料理の「山川漬」の材料として使われます。
江戸時代から県南部の山川地方で栽培されて、県により「かごしまの伝統野菜」に認定されています。
福岡
かつお菜
福岡県を中心に栽培されているアブラナ科の葉野菜で、高菜の仲間です。
福岡の伝統野菜で、博多の雑煮には欠かせない野菜として知られています。
葉はやわらかく風味があり、葉面が縮んでいます。
辛みがなく、アクが少ないのも特徴です。
旨みが多く、煮るとほんのり甘みも感じられます。
和え物・漬物や煮物、鍋料理に炒め物と幅広く活躍する野菜です。
抗酸化作用が高く、他の葉野菜の中ではカルシウムを多く含んでいます。
アミノ酸も多く含まれています。
大庭春菊
北九州市小倉南区で栽培されている春菊の品種で、葉に丸みがあり、アクや苦みが少ないのが特徴です。
別名「鍋旬ぎく」とも呼ばれ、鍋物や汁物、サラダなど幅広く利用されています。
βカロテン、ビタミンC、カルシウムなど多くの栄養が含まれており、サッと茹でてポン酢で食べたりサラダに入れることもあるそうです。
佐賀
青縞瓜(あおしまうり)
佐賀県多久市を中心に栽培されている伝統野菜で、主に漬物として利用されます。
青大縞瓜とマクワウリの自然交雑種で、果皮は灰緑色に銀色の縞模様をしています。
果肉は黄緑色で厚く緻密で、歯切れが良いです。
酒粕に漬けて1ヶ月以上寝かせたあと、青しまうり漬けとして出荷されるため、酒粕特有の香りとカリッとした歯ごたえが特徴です。
贈答用などで人気があります。
唐津自然薯(からつじねんじょ)
佐賀県唐津市で栽培される山芋の品種で、赤土の土壌で育つのが特徴です。
粘り強く、美白・美肌効果があることから、古くから縁起物として親しまれてきました。
山菜の王様と呼ばれるほど栄養価が高く、独特の粘りと風味は長いもや大和芋とは比較にならないそうです。
長崎
紅大根(あかだいこん)
長崎県を代表する伝統野菜で、カブの一種です。
形が大根に似ていることからこの名前がつきましたが、赤鬼の腕に似ていることから「鬼の手大根」とも呼ばれます。
歯ごたえがあり、すっきりした味わいが特徴です。
ビタミン類をはじめ消化を助けるジアスターゼなどの酵素が豊富で、葉にもカルシウムや鉄分などのミネラルが多く含まれます。
長崎白菜
長崎の伝統野菜で、別名「唐人菜(とうじんさい)」とも呼ばれます。
中国山東省から伝来したと言われ、長崎の食文化に欠かせない野菜です。
葉が巻かないため柔らかく、独特の風味があります。
雑煮、鍋物、おひたし、漬け物などに活用されます。
熊本
水前寺もやし
熊本県の伝統野菜で、正月の雑煮に欠かせない具材として親しまれています。
シャキシャキとした歯ざわりが特徴で、ミネラルや食物繊維などが豊富に含まれています。
通常のもやしよりも大きく、35cm前後で収穫されます。
長寿と健康を願う縁起物でもあります。
あかどいも
熊本県阿蘇地方で栽培されている里芋の一種で、赤い葉柄(茎)を食用とするものです。
葉柄を塩漬けして作る「あかど漬け」は、阿蘇地方の伝統食として知られています。
鮮やかな赤色とザクッとした食感が特徴で、独特の酸味と歯ごたえがあります。
馬刺しと色合いや食べ方が似ていることから、「畑の馬刺し」「阿蘇の馬刺し」とも呼ばれます。
宮崎
白皮苦瓜(しろごーや)
白い果実が特徴のゴーヤ(苦瓜)の品種です。
苦みが少なく、サラダなど生でも食べやすいのが特徴です。
ビタミンCやカロテン、食物繊維が豊富で、免疫力を高めたり、肌の健康を保つのに役立つほか、夏の暑さで疲れた体をリフレッシュさせる効果があります。
糸巻大根
宮崎県西米良村で古くから栽培されてきた伝統野菜で、根に赤紫色の縞模様が入るのが特徴です。
地元では「米良糸巻大根」「米良大根」とも呼ばれます。
糖度が普通のダイコンより2~3度高く、肉質が緻密でやわらかいのが特徴です。
煮崩れしにくく、サラダにも適しています。甘みが強く、生で食べたり、大根おろしやなます、煮物、切り干しなどに幅広く利用されます。
煮物にすると味が染みやすく形崩れしにくいので、猪汁や煮しめ、おでんの具材にも欠かせない野菜です。
以上

私は視覚と聴覚に障害があり、視覚障害については全盲です。
当事者の一人として、皆様に白杖や点字ブロック以外のことも知っていただけたらと思い、視覚障害者が利用しているツールについてご紹介していこうと考えています。
皆さま、どうぞよろしくお願い致します。