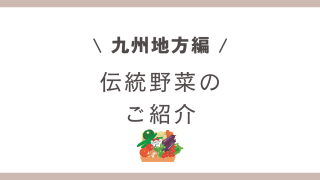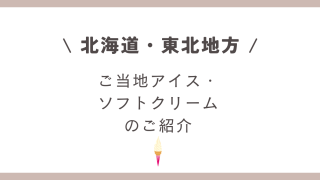メゾン・シンビーオ(在宅就労の豆知識部屋)
中国地方のお雑煮
こんにちは、本記事では中国地方各県のお雑煮の特徴をご紹介します。
岡山
大きく分けて「県南」と「県北」で特徴が異なります。
県南地域のお雑煮
具材:丸餅(焼かずに煮るのが一般的)ブリ(出世魚であるため縁起が良いとされる)、ハマグリ
出汁:鰹節と昆布でとるすまし汁が主流です。
味わい:鰹と昆布の旨みが効いた、あっさりとした優しい味わいです。
県北地域のお雑煮
具材:丸餅(焼かずに煮るのが一般的)
ブリ(県南同様、出世魚として)、スルメ(出汁をとった後、身も具材として食べられる)、大根、にんじん、ほうれん草などの根菜類。
出汁:スルメでとるのが大きな特徴です。
昆布も一緒に使うことがあります。
味わい:スルメから出る独特の香ばしさと、しっかりとした旨が特徴です。
県南に比べて、より個性的な風味を楽しむことができます。
鳥取
同じ県内でも地域によって驚くほど特色が異なります。
大きく「東部」「中部」「西部」の3つに分けられ、特に東部から中部にかけての海岸部では全国的にも珍しい「小豆雑煮」が主流です。
東部地域のお雑煮(鳥取市、岩美町、八頭郡など)
出汁:小豆を煮た汁。
基本的には小豆の甘みがメインであり、昆布や鰹節で出汁をとることはありません。
具材:丸餅(焼かずに柔らかく煮るのが一般的)と小豆。具材は非常にシンプルで、餅と小豆のみ、またはごく少量の具材(栗や金時豆などを加える家庭もまれにあります)が入る程度です。
味わい:見た目はぜんざいやおしるこのように、砂糖で甘く味付けされた小豆の汁に餅が入っています。
塩気のあるおせち料理との対比で、この甘さが好まれます。かつては砂糖が貴重であったため、正月のご馳走として甘い小豆雑煮が食べられていたという歴史があります。
中部地域のお雑煮(倉吉市、東伯郡など)
出汁:東部と同様に、小豆を煮た汁が主流です。:
具材:丸餅(焼かずに柔らかく煮るのが一般的)
三朝町では、その地域特産の「とち餅」を用いるのが特徴的です。
主な材料は小豆で、東部と同様に、小豆雑煮が主流です。
山間部の一部の地域では、醤油味や味噌味の雑煮も存在し、野菜などの具材が入ることもあります。
東部と同様に甘い小豆雑煮が主流ですが、家庭や地域によって甘さの程度が異なります。
とち餅を使う場合は、とちの独特の風味と香ばしさが加わります。
山間部ではすまし汁や味噌仕立ての雑煮も食べられ、素朴で優しい味わいです。
西部地域のお雑煮(米子市、境港市、大山町、日野郡など)
出汁:醤油ベースのすまし汁が主流です。
ブリや鶏肉、赤貝などの具材から出る旨みが加わります。
具材:餅は、丸餅(焼かずに柔らかく煮るのが一般的)です。
メインは、ブリ(出世魚として縁起物)、豆腐、ネギ、ゴボウなどの根菜類が一般的です。
ブリの他に鶏肉、赤貝、かまぼこ、そして「かもじのり(島根県産の高級海苔で、酒で溶いてかけたり、そのまま散らしたりする)」を入れる地域もあります。
また、サメ肉を入れる地域もあります。
味わい:東部や中部とは異なり、甘くない醤油ベースのすまし汁が中心です。
多様な具材から出る出汁の旨みが特徴で、あっさりとしていながらも深みのある味わいです。
かもじのりが加わる場合は、磯の香りが豊かに広がり、独特の風味を醸し出します。
島根
すまし雑煮(醤油味)
出汁と味:カツオ、昆布、イリコ(煮干し)、あるいはトビウオ(アゴ)などからとる醤油ベースのすまし汁です。
具材:丸餅を使い、特に海沿いの出雲地方などでは、高級品の岩のり(十六島紫菜)とカツオ節をたっぷりかけて、磯の風味を楽しむのが特徴です。
餅は焼かずに煮て柔らかくします。
小豆雑煮(甘い)
出汁と味:ぜんざいに近い、甘く煮た小豆の汁を使いますが、ぜんざいよりはサラッとしているのが特徴です。
具材:丸餅のみを入れるシンプルなものです。
広島
瀬戸内海の豊かな海の幸を生かした、華やかなお雑煮が主流です。
出汁と味:煮干し、昆布、カツオなどからとる醤油ベースのすまし汁が基本です。
具材:広島名産の牡蠣(かき)(「福をかき取る」縁起物)と、ぶり(塩ぶり)が二大看板です。これに大根、人参、水菜などの野菜を加え、丸餅は焼いて入れることが多いです。地域によっては焼きあなごやハマグリを入れることもあり、豪華で海の旨味がたっぷり詰まったお雑煮です。
山口
かぶ雑煮
出汁と味:煮干し(いりこ)で出汁をとり、醤油で味を整えたすまし汁です。
具材:丸餅(焼かない)と、縁起物である白いカブ(円満を願って輪切りに)がメインです。
さらに、スルメ(寿留女:長寿を願う)を細く切って加えるのが大きな特徴です。
餅を煮るため、汁にとろみがつくこともあります。
シンプルで優しい味わいが魅力です。
以上

私は視覚と聴覚に障害があり、視覚障害については全盲です。
当事者の一人として、皆様に白杖や点字ブロック以外のことも知っていただけたらと思い、視覚障害者が利用しているツールについてご紹介していこうと考えています。
皆さま、どうぞよろしくお願い致します。