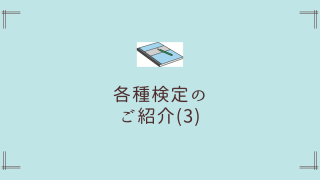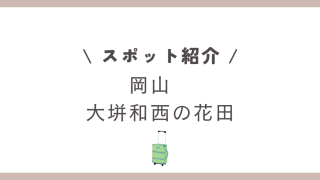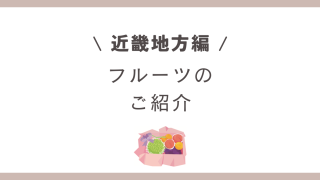メゾン・シンビーオ(在宅就労の豆知識部屋)
北海道と東北のシンボルとなっている生き物
こんにちは、本記事では北海道と東北地方各県のシンボルとなっている生き物をご紹介します。
北海道
タンチョウ
美しい純白の羽と頭頂部の赤い皮膚が特徴的な北海道を代表する鳥で、北海道のシンボルとして道民からも愛されています。
日本の野鳥の中で最も大型の鳥で全長は約140cm、体重は10kg前後です。
白い羽毛に覆われており、頭頂部の鮮やかな赤が特徴的で漢字では「丹頂」と書きます。
「丹」は赤、「頂」は頭という意味で、頭頂部の色が由来です。
古くからアイヌの人々にも「サロルンカムイ(湿原の神)」として大切にされてきました。
また、夫婦円満のシンボルとしても尊ばれています。
1924年まで絶滅したとされていた時期もありましたが、保護活動によって生息数が回復し、現在では1,000羽を超える個体数が見られるそうです。
青森
ハクチョウ
北国に冬を告げる鳥として県民に親しまれている鳥です。
主にオオハクチョウとコハクチョウが飛来し、11月上旬にシベリアなどから渡来して春の訪れとともに帰国します。
コォーなどと大きく甲高い声で鳴きます。
水面を優雅に泳ぐ姿や大空を飛ぶ姿は美しいとされており、油脂腺から分泌される油を羽に塗ることで撥水性を持ち、水中に浮かぶことができるそうです。
岩手
南部鮭
主に県内の河川で育てられる鮭で体長は約90センチメートル、体は紡錘形(ぼうすいけい)をしています。
鮮やかなオレンジ色をしており、刺身や塩焼きなど様々な料理に活用されます。
三陸・海の博覧会の開催を記念して平成4年2月に県の魚に選ばれました。
江戸時代には南部藩の重要な財源とされた鮭で、今でも岩手県のシンボルとして重要視されています。
宮城
雁(ガン)
カモ目カモ科に属する水鳥であり、特にマガンとシジュウカラガンがよく知られています。
マガンは宮城県の蕪栗沼(かぶくりぬま)や伊豆沼で越冬する大型の水鳥で、体長は約72cm、翼開長は約1.4mになります。
日本に渡ってくるマガンの約70%が宮城県の蕪栗沼・伊豆沼周辺で越冬するそうです。
飛ぶ時に「雁行」と呼ばれる隊列を形成するのが特徴で、マガンは国の天然記念物に指定されています。
シジュウカラガンは小型のガンで、頬に白い模様があります。
(かつて日本に最も多く渡ってくるガンの一種でしたが、現在では減少傾向にあります)
山形
サクラマス
ヤマメの1種です。
川で育ったヤマメが海へ下り、再び川に戻ってきて産卵する「降海型」で、銀白色に輝く体色と産卵期に現れる薄いピンク色の模様が特徴です。
サクラマスのオスは上あごが少し曲がっているのが特徴です。
桜の季節に川を遡上するため「サクラマス」と呼ばれており、脂がのっていて美味しいとされ、素焼きや餡かけ料理として食べられています。
秋田
ハタハタ
深海魚で水深200mよりも深い場所に生息しています。
体長は15~20cmほどで左右に扁平な体型をしており、背中には不定形の褐色の斑紋があります。
淡白な味わいとツルッとした舌触りが特徴の魚で、特に秋田県では塩焼きや醤油煮、しょっつる鍋など様々な料理に利用されています。
身離れが良く、火を通すと骨と身が簡単に離れるため、食べやすいのも特徴です。
民謡「秋田音頭」にも歌われるほど、県民の生活に深く根差している魚です。
福島
キビタキ
その美しい姿と鳴き声、そして生態系への貢献から福島県民に親しまれている鳥です。
オスは橙色、黒色、黄色を帯びており、美しい声で鳴きます。
メスは全体が緑褐色でオスとは異なる模様を持ちますので、オスとメスの見分けがつきやすい鳥でもあります。
4月から10月にかけて福島に渡来し、低山帯や落葉広葉樹の自然林に生息します。
キビタキは害虫を食べるなど、森林の生態系に貢献する役目も担っています。
以上

私は視覚と聴覚に障害があり、視覚障害については全盲です。
当事者の一人として、皆様に白杖や点字ブロック以外のことも知っていただけたらと思い、視覚障害者が利用しているツールについてご紹介していこうと考えています。
皆さま、どうぞよろしくお願い致します。